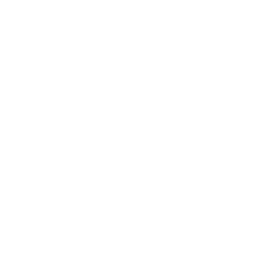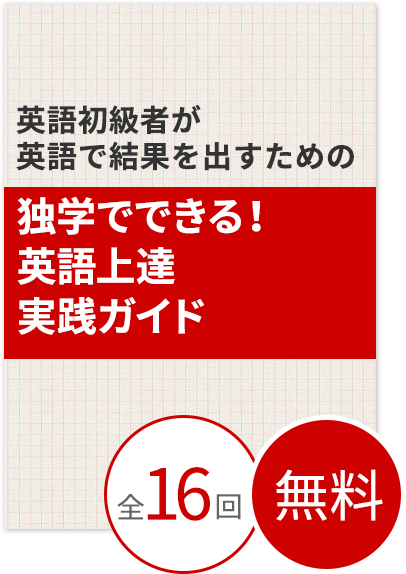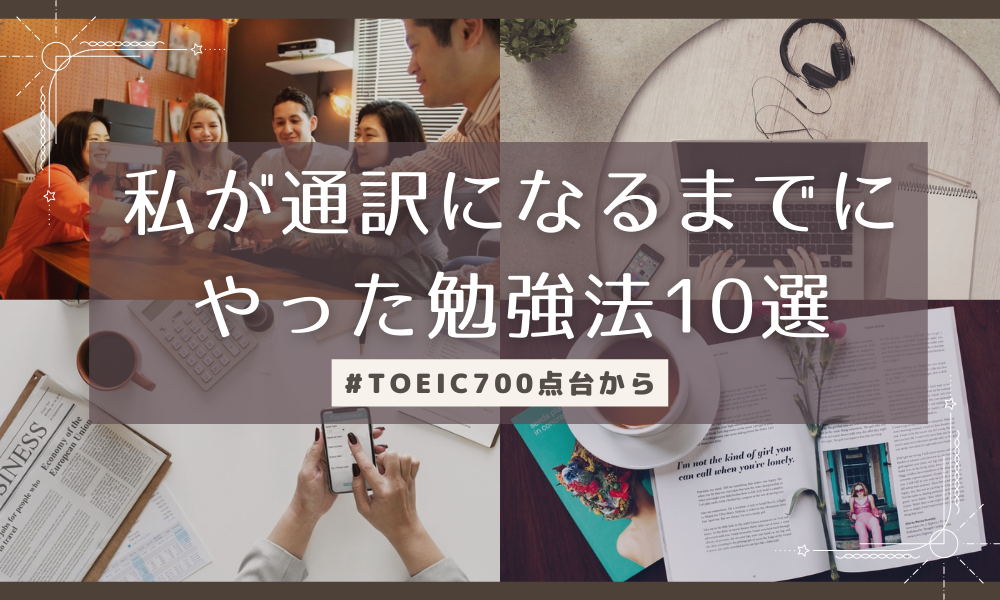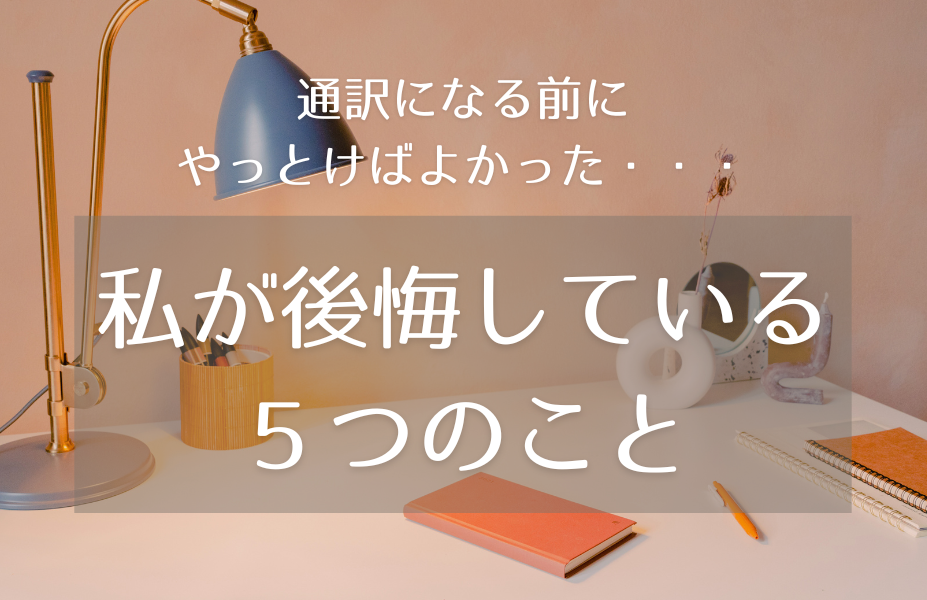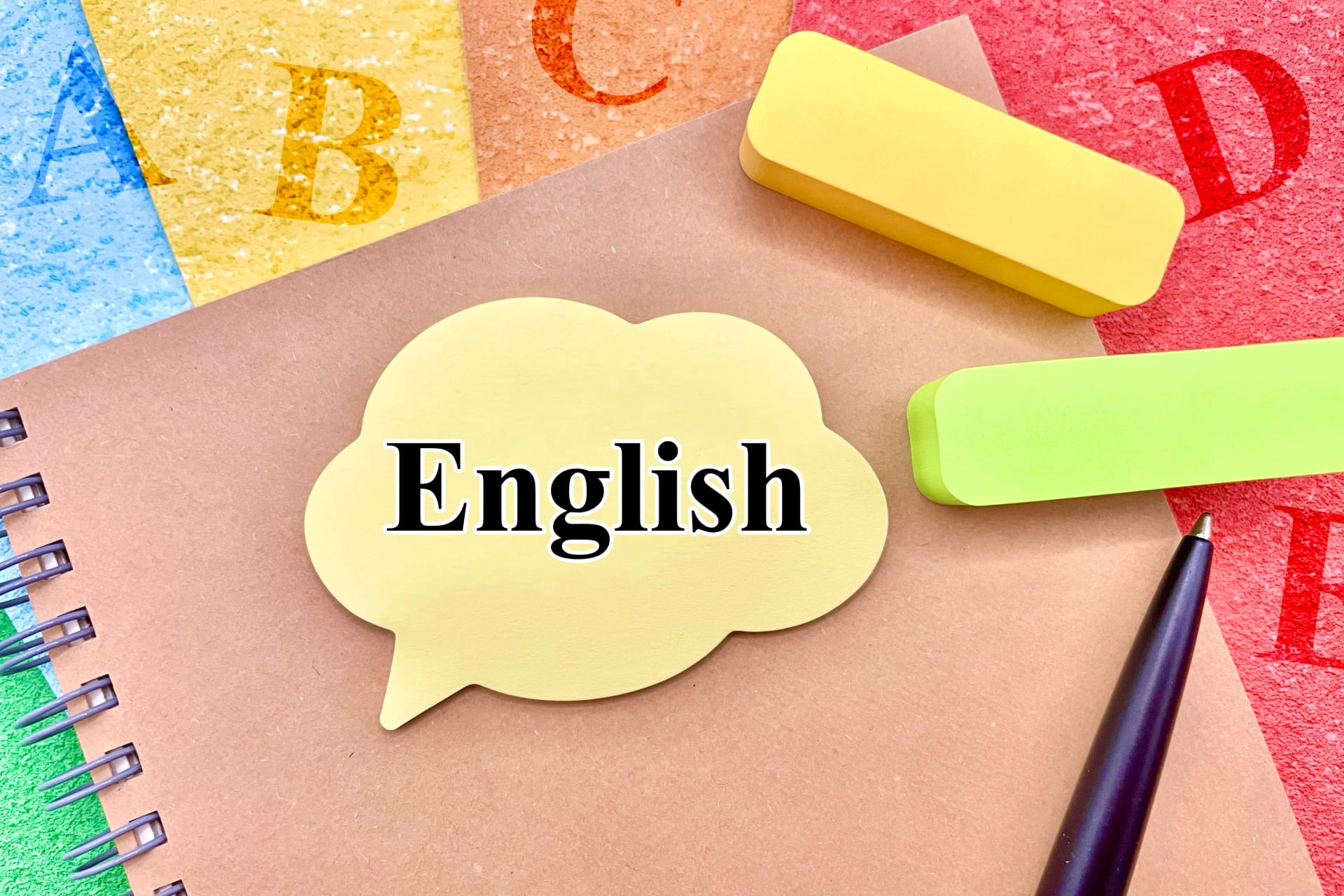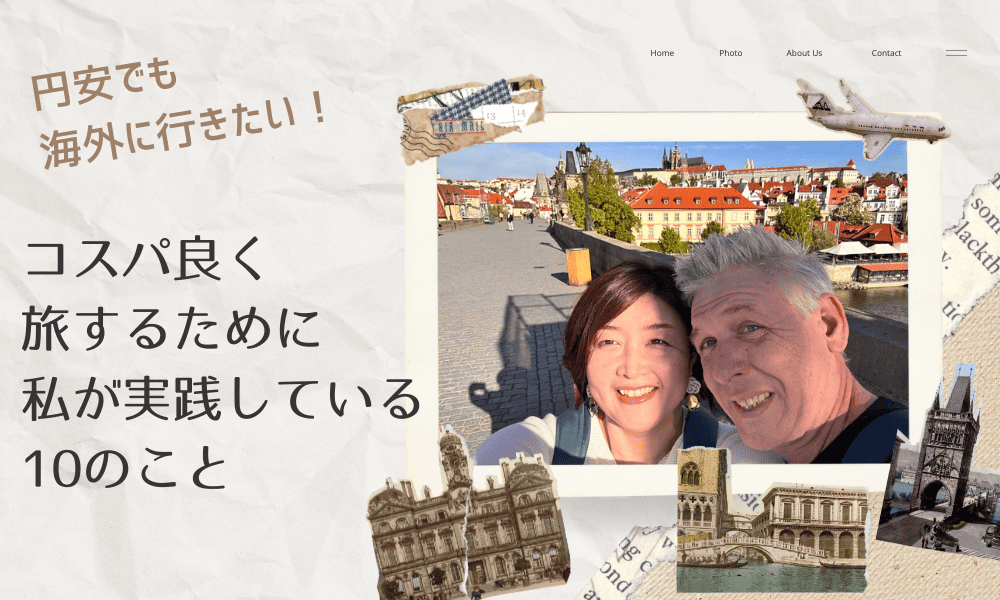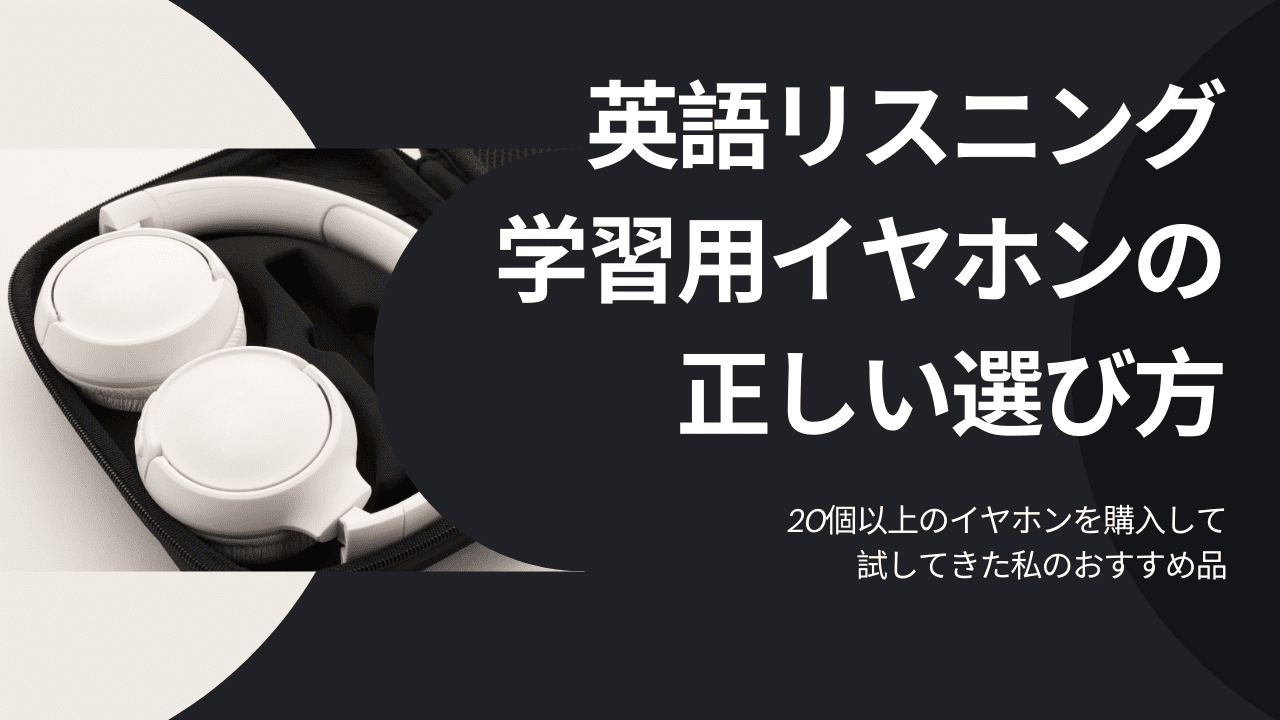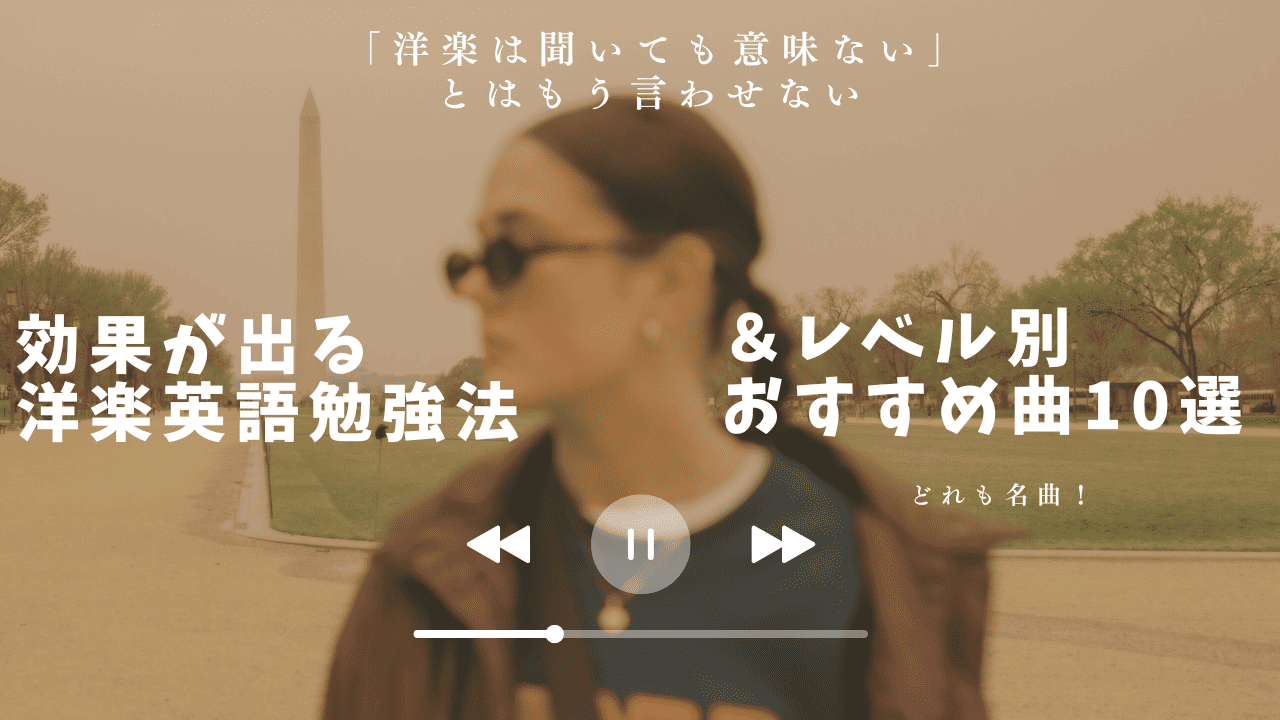2022年6月25日
私が通訳になるためにやらなかった/必要なかった勉強法10選
 エバンス愛
エバンス愛
※当ブログ記事には、広告が含まれます。

私がTOEICが780点だった25歳の時から、31歳で通訳者として採用されるまでの6年間でやった勉強法を、私がTOEIC700点台から通訳になるまでにやった勉強法10選にまとめました。
そこで今回は、「私がTOEIC700点台から通訳になるまでにやらなかったこと」を書いてみたいと思います。
「世間的には通訳者には必要と思われているようだけど、私はやらなかったし、別に必要なかったな」「これをやらなかったからこそ結果的に良かったのかも」と思う勉強法です。
コンテンツ
1.音読・オーバーラッピング
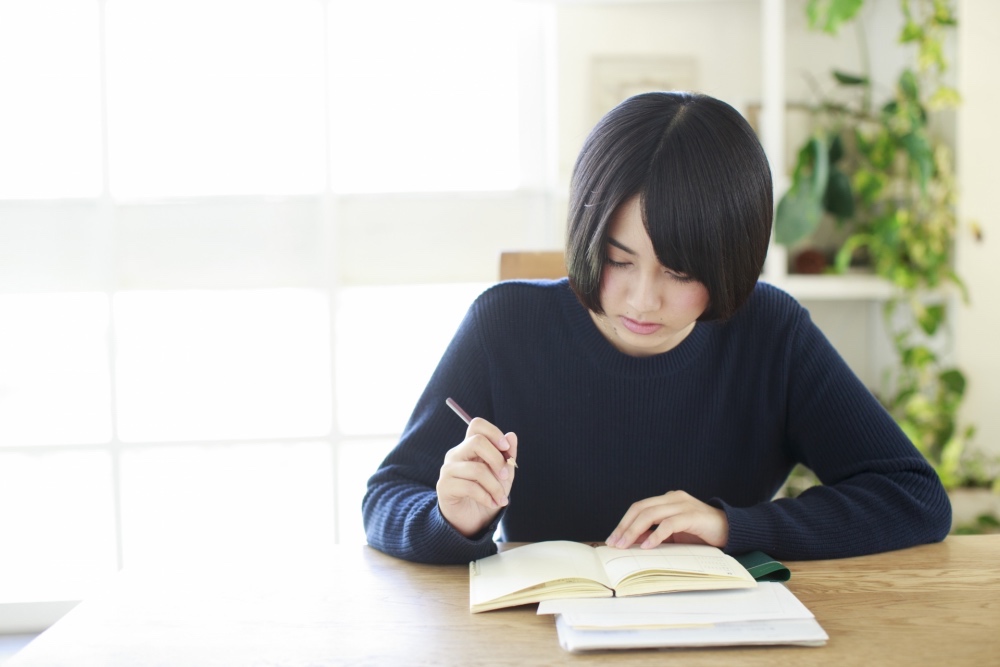
私がTOEIC700点台から通訳になるまでにやった勉強法10選でも話しましたが、純粋に勉強に取り組める時間があるなら、シャドーイングより音読が効果が高かったかもしれません。
でも、フルタイムで勤めていると、仕事から疲れて帰ってきて、「さあ、机について音読をやろう」「さあ、これからオーバーラッピングをやろう」という気には正直なかなかなれないです。
なので、私は音読やオーバーラッピングにほとんど時間を使っていません。
私には通勤時間に車の中でできるシャドーイングで、音読の代わりとなるトレーニングがしっかりできていたようです。
もちろん、どんなに忙しくても時間は作れるものだし、音読やオーバーラッピングもやらないよりやったほうがよかったには違いありません。でも、音読やオーバーラッピングをやらなくても一応通訳として採用される程度になったという意味で「私には必要なかった勉強法」として音読とオーバーラッピングを挙げたいと思います。
音読とオーバーラッピングの、シャドーイングとの効果の違いについてはこちらをどうぞ。
・音読とシャドーイングの効果の違いとメリット・デメリット
・オーバーラッピングとシャドーイング、やるならどっち?効果の違いを解説
2.発音に特化した訓練

「通訳者になるなら、発音はネイティブレベルでないといけない」と多くの人が思っています。
が、私の知る通訳者は、必ずしも発音が上手な人ばかりではありませんし、みんなが発音の特別な訓練をしているわけでもありません。
もちろん、発音が下手よりはうまい方がいいに決まっているし、努力が必要なのは言うまでもないことです。でも、「クライアントが聞き取りに苦労するほどのひどい発音でなければ、大きな問題はない」というのが、私の経験から言えることです。
多くの人が勘違いしていることですが、発音とは、「r」の舌の動きとか、「v」と「b」の違いとか、一つ一つの音の出し方が重要なのではありません。
文章全体のリズムや強弱、イントネーションのほうがずっと重要で、それらさえきちんと押さえられていれば「v」となるべき音が「b」となっていても普通に通じます。意外かもしれませんが、これほんと。
LとRの違いは大事じゃない!発音に重要なのは「リズム」に書いていますが、文章全体のリズム、強弱、イントネーションなどの訓練は、私の場合はシャドーイングだけで問題なくできたと思っています。
3.専門用語や専門知識習得のための英雑誌の購読

「通訳者になりたければ、TIMEとかNewsweekなどの英雑誌を購読するのは常識。あらゆる分野の専門単語を知っておく必要があるし、世界の政治経済、環境問題などあらゆる分野に精通していなければ」と思っている人も多いと思いますが、これも誤解です。
業界それぞれの専門用語や知識の習得は必要ですが、「あらゆる分野の深い知識やボキャブラリー」は必要ありません。国連の第一級の通訳者さんとかなら話は別ですが、普通の企業の会議通訳の場合、世界の政治経済や環境問題の英語に精通している必要はありません。
「私の経験では」という話になりますが、英検1級レベルの単語が通訳現場で必要な場合など、ほとんどありません。通訳とは「話し言葉」を訳すことなので、その業界の専門用語を除いてはそんなに難しい単語が飛び交うわけではなく、一般的な単語がほとんどです。
4.英英辞典の利用
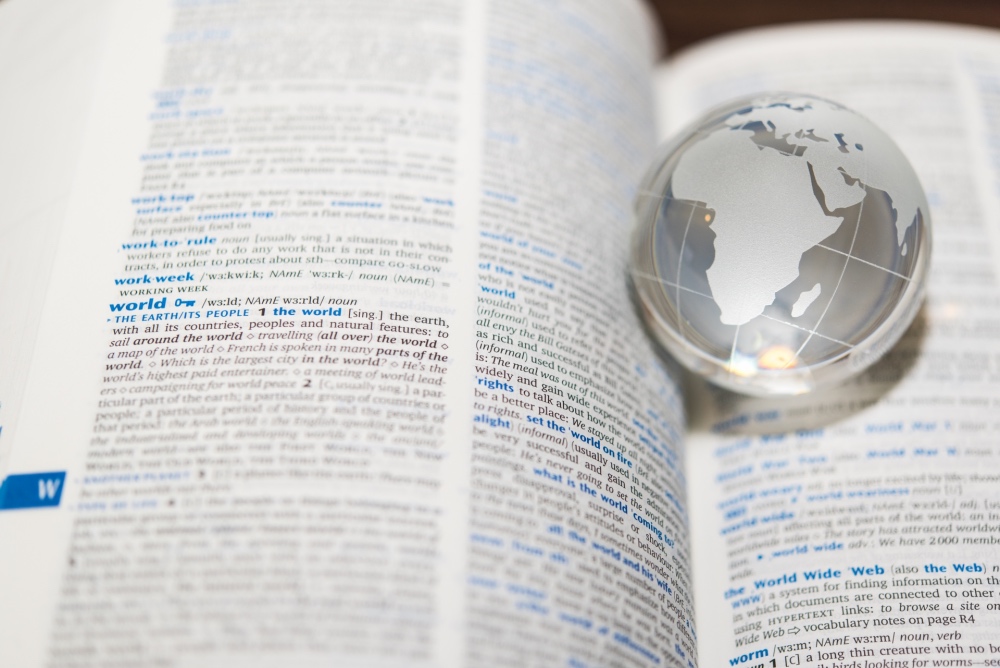
「英語ができるようになりたければ英和辞典は使うな」という話をよく聞きますし、英英辞典を使うことの効果も理解できます。
が、問題は、知らない単語が出てきたときに、いちいち英英辞典を調べてその意味を理解し、場合によっては英英辞典の定義をノートに書き出したりといった勉強が続けられるかどうかということです。
私は続けられなかったので、英英辞典の利用は早々にあきらめました。(;・∀・)
今までずっと英辞郎を使っていますが、別に問題は感じていませんし、「英英辞書を使っていればもっと早く通訳になれたかも・・・」とも特に思わないなというのが正直なところです。なので、英英辞典を使うかどうかは好みでいいのではないかな。
英英vs英和辞典、英語学習に効果的なのはどっちか徹底比較してみたで、英英辞典の使い方について書いています!
5.TOEIC対策

私は、TOEICに特化した勉強は一切していないです。普通にやるべき勉強を積み重ねていったら、勝手に高得点を取ることができました。
TOEIC対策が根本的な英語力の向上に直結しているならいいのですが、それがTOEICの問題の解き方だったり点取りテクニックだと全く意味がないです。
通訳者の英語レベルの目安としてTOEIC900点台というのをよく聞きますが、TOEIC900点になれば通訳者になれるわけではありません。TOEIC高得点を目指して勉強をしているようでは、通訳レベルにはまだまだというのが正直なところで、900点台になってようやく、「通訳を目指して勉強するスタートラインに立てた」というところです。
「通訳を目指すなら、簡単に900点が取れないようでは話にならない」と知人のフリーランス通訳者が言っていましたが、その通りだと私も思います。
英語転職に有利になる資格は?【TOEIC900なんていらない】の記事もあわせてどうぞ!
6.いい勉強法を求めて情報を捜し回ること

勉強法の情報を提供している立場でこれを言うのは心苦しいですが、勉強法探しに時間を費やすばかりで肝心の勉強をしてない人が多すぎると感じます。
私の場合、「この勉強法をやろう」と決めたら、それを愚直にやり続けました。「他に、私がまだ知らないもっと効果的な方法があるのでは?」なんて考えたこともありませんでした。
たとえば、シャドーイングという勉強法があると知ってすぐにそれに取り組み始めて、結果的に10年以上継続しました。
当時、仮にシャドーイング以外の勉強法があると知ったとしても、「シャドーイングすら満足にできないのに他のことに手を出してどうする!」とおそらくスルーしたのではないかと思います。
自分のやり方に自信があったわけでも何でもありません。単に、勉強法を探す時間が惜しかっただけです。
7.教材の選定に時間をかけること

私は、本屋さんでいろんな英語教材を見て回ったり、ネットでいろんな通信講座の評判を見て検討したりということを全くと言っていいほどしませんでした。
信頼する人が勧めてくれた教材、信頼する会社の作っている教材、それだけを常に選んでいました。それ以外の教材は選択肢にそもそも入れていません。
だから、本屋さんでブラブラ、ネットでウロウロというのはほぼしていないです。
読者さんのメールを読んでいると、特定の教材を実践するかしないかで数ヶ月(時には数年単位で)悩んでいる人がいます。「それだけの時間を教材選びじゃなく、真剣にその教材に取り組むことに使っていたら、どれだけの違いが生まれているか!」と本当に残念に思います・・・
教材選びに時間をかけるのは、本当にもったいないです。
うまくいったらそれでいいし、結局自分に合わないと分かったとしても、その時間は無駄ではありません。次回はもっと良い選択ができるようになるからです。
何もしないで「どうしよう、やろうかな、やめようかな」が一番無駄な時間です。
8.通訳者養成講座

通訳者になりたい人に「通訳養成講座に通ってはいけない」と言うつもりは全くないです。
通えるなら、通った方がいいに決まっています。そもそも、専門的な通訳トレーニングを受けたこともない人が、通訳として採用されるチャンスは小さいという現実的な問題もあります。
が、トレーニングを受けずに飛び込んでしまった私が「今からでもスクールに通うべきか」と先輩に相談したとき、通訳スクールに通った経験のある先輩にこう言われました。
「学校の課題で覚えさせられた政治の単語とかは、結局うちの仕事にはほぼ関係なかったし、実際にここで仕事をすることほど役に立つ訓練はなかった」と。
私が運営している翻訳エージェントで翻訳の仕事をしてもらった女性も、「翻訳の通信講座も受講しましたが、実際に愛さんの翻訳チームで仕事をしたのが何百倍も勉強になったし力がつきました」と言っていました。
勇気とチャンスと環境さえあれば、OJT(日常業務を通じたトレーニング)にまさるものはないと思います。
9.資格取得や試験合格に時間を費やすこと

私が英検1級に合格したのは、通訳として働き始めた後です。通訳ガイドの試験や翻訳検定を受けたことも、そのために勉強したこともないです。
「通訳になるのが目標なので、まずはTOEIC900点と英検1級を目指しています」「通訳になる前のステップとして、まずは通訳ガイドの資格を取ろうと思います。そのためには、通訳ガイドの英語試験が免除になる英検1級の合格を目指したいと思います」
というメールを結構よくいただくのですが、「なんでそうやってわざわざ遠回りするかな?」と私は不思議に思っています。
・・・いや、実は理由はよく分かっています。
ズバッと言っちゃいますが、「その目標と正面から向き合うのが怖いから、試験の合格を目指すことで本当の目標から逃げている」んですよね。私もそういう心理状況に陥ったことが何度もあります。怖い、逃げたいという気持ちは痛いほどわかります。
でも、通訳ガイドになりたい人以外は通訳ガイドの試験に合格する必要はないし、英検1級なんて何になるにも必要ありません。
通訳翻訳に英検1級は有利?「もう少し勉強してから」は禁句にしようも、ぜひ読んでみてください。
10.英語圏への留学(長期滞在)

私は、カナダのモントリオール(フランス語圏)で2か月ほど英語教授法を学んだ経験はあります。でも、教室以外ではフランス語だし、週3日、1回当たり半日のパートタイムコースだったので、留学と言えるほどのものでもありません。
通訳者になるには、長期の留学経験があるか、帰国子女でなければならないのではと思われがちですが、全然そんなことはありません。
「留学経験がない」ということを必要以上にマイナス要素と考えている人が多いですが、留学経験なしでも英語のプロはたくさんいます。
これは、逆に英語圏での長期滞在や留学経験のある人に聞いてみたらいいですよ。「数年くらい留学とか滞在とかしても、そんな変わらないよ」ってみんな言いますから。(;・∀・)
経験したことない人からすると「数年間も住んで、変わらんわけないじゃない!」って思いますよね。もちろん全く進歩がゼロってことはないはずです。
でも、「留学したことないから、自分は高い英語力を身につけることができないんだ」と思っているなら、それは全く違うということです。
私が通訳者になるまでにやらなくて良かったなと思うこと
ここからは、おまけで「通訳者になるためにやらなくて良かったなと思うこと」コーナーです。やったけど、通訳になるには必要なかったということですね。
1.英字新聞の購読

TOEIC700点、800点台の頃に英字新聞を購読していたことがあるのですが、ほとんど廃品回収に直行でした。ほんともったいないことしました・・・(;・∀・)
辞書で一生懸命知らない単語を調べつつ、1日に1記事読むのが精いっぱいでした。しかも、それを毎日やったわけでもないですし。
今だったら、まともに読めもしない英字新聞に月々3,000円も払うくらいなら、ネットでいくらでも手に入る英文記事を使うと思います。
ただし、外資系企業で秘書兼翻訳の仕事をしていた時(TOEIC980点を取得して数年後)は、上司のお古の英字新聞を持って帰って読んでましたが、その頃に自分で購読していたらもっと有効活用できたと思います。
英字新聞に載っていた翻訳コンテストにもその時に応募していました。
でも、やっぱり毎日そんなにたくさんは読めないので、英字新聞を購読するとしても、週刊で十分だと個人的には思います。
2.英語教授法

英語を教えるという目標がない人にも、英語教授法の講座を検討する人が結構いるようなのですが、まあ、通訳になるには全然関係ないです。というか、英語の先生になりたい人以外には全く勧めないです。
私自身は、英語教育に携わる者としてスキルアップのために受講したので、勉強自体はすごく役に立ちました。「通訳になるには」全く不要だったということです。
私がカナダのモントリオールで英語教授法のコースに通っていた時、日本人は私一人で、あと韓国人の女の子が一人いました。
残りは、最も多かったのがカナダ人(英語ネイティブか、仏語ネイティブの英仏バイリンガル)とアメリカ人、そして英語がめちゃくちゃ上手なオランダ人でした。まあ、英語の先生になるコースだから英語がネイティブレベルの人ばかりで当たり前なのですが・・・
で、その韓国人の彼女は、英語の先生になりたいのではなく、将来は通訳になりたいと言っていました。でも、語学コース(普通の語学留学生向け)は簡単すぎてレベルが合わないので、英語教授法のコースを受講していると言っていました。
英語教授法のコースはノンネイティブも受講可能でしたが、入学試験の受験資格がTOEIC900点以上でした。入学試験には英語の文法や語法を説明する筆記試験と、口頭試験がありました。
生徒の大半はネイティブレベルなので、授業では英会話の練習なんかは当然全くないし、英語の「教え方」のスキルを高めるための講義やディスカッション、グループワークばかりです。
また、併設されている語学学校の実際の授業を見学して、その教授法についてレポートを書いたり、模擬授業(いわゆる教育実習)もありました。課題が多く、修了試験の準備も大変で、ネイティブでもドロップアウトする人がいました。
私は「もう嫌だ、辞めようか」と何度も何度も思いながらも何とか頑張りましたが、韓国人のクラスメイトは途中でドロップアウトしてしまいました。
私にとってはとてもいい経験になりましたし、最終的には”with distinction”(優等賞?)の成績で修了できましたが、このコースのおかげで英語が上手になったか、通訳になるのに役立ったかと言われれば、そんなことはないです。
それよりも、英語を教えるということにそれほど興味も情熱もないのに、それについて英語でレポートをたくさん書いたり、ネイティブに向かって英語で模擬授業をするのはかなりしんどいです。
なので、英語教授法のコースは、英語の先生を目指す人や教えるスキルを向上したい人以外にはかなり損な苦労になってしまうと思います。
まあ、英語教授法だけでなく何の分野で留学しても、興味のないことを(日本語で勉強するのもつまらないだろうに)英語で勉強するのがしんどいのは、きっと同じですね。
私がTOEIC700点台から通訳になるまでにやらなかった10のことまとめ
いかがだったでしょうか?以下が、私が「通訳になるために必要なかったな」と思うことです。
1.音読
2.発音に特化した訓練
3.専門用語や専門知識習得のための英雑誌の購読
4.英英辞典の利用
5.TOEIC対策
6.いい勉強法を求めて情報を捜し回ること
7.教材の選定に時間をかけること
8.通訳者養成講座
9.資格取得や合格に時間を費やすこと
10.英語圏への留学(長期滞在)
そして、やったけど通訳には関係なかったなと思うことは、以下です。
1.英字新聞の購読
2.英語教授法
これから通訳のお仕事を目指す人が、無駄な勉強をしないためにお役に立てていただけるとうれしいです。
なお、TOEIC700点台から通訳になるまでの6年間を振り返って、「やらなかったけど、やっといたら良かった」と思うこともまとめています。こちらも、良かったらどうぞ。
▶「通訳になる前にやっとけばよかった!」と後悔している5つのこと