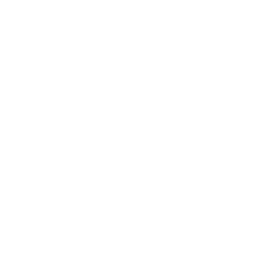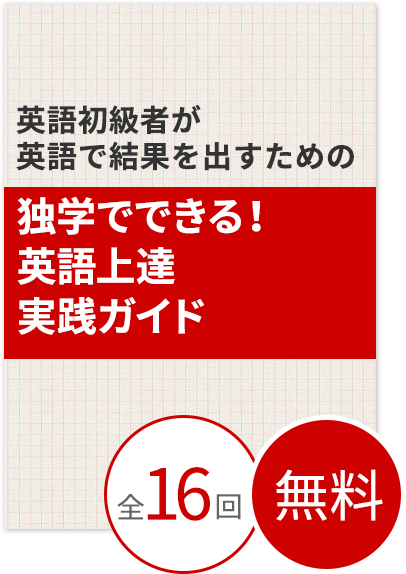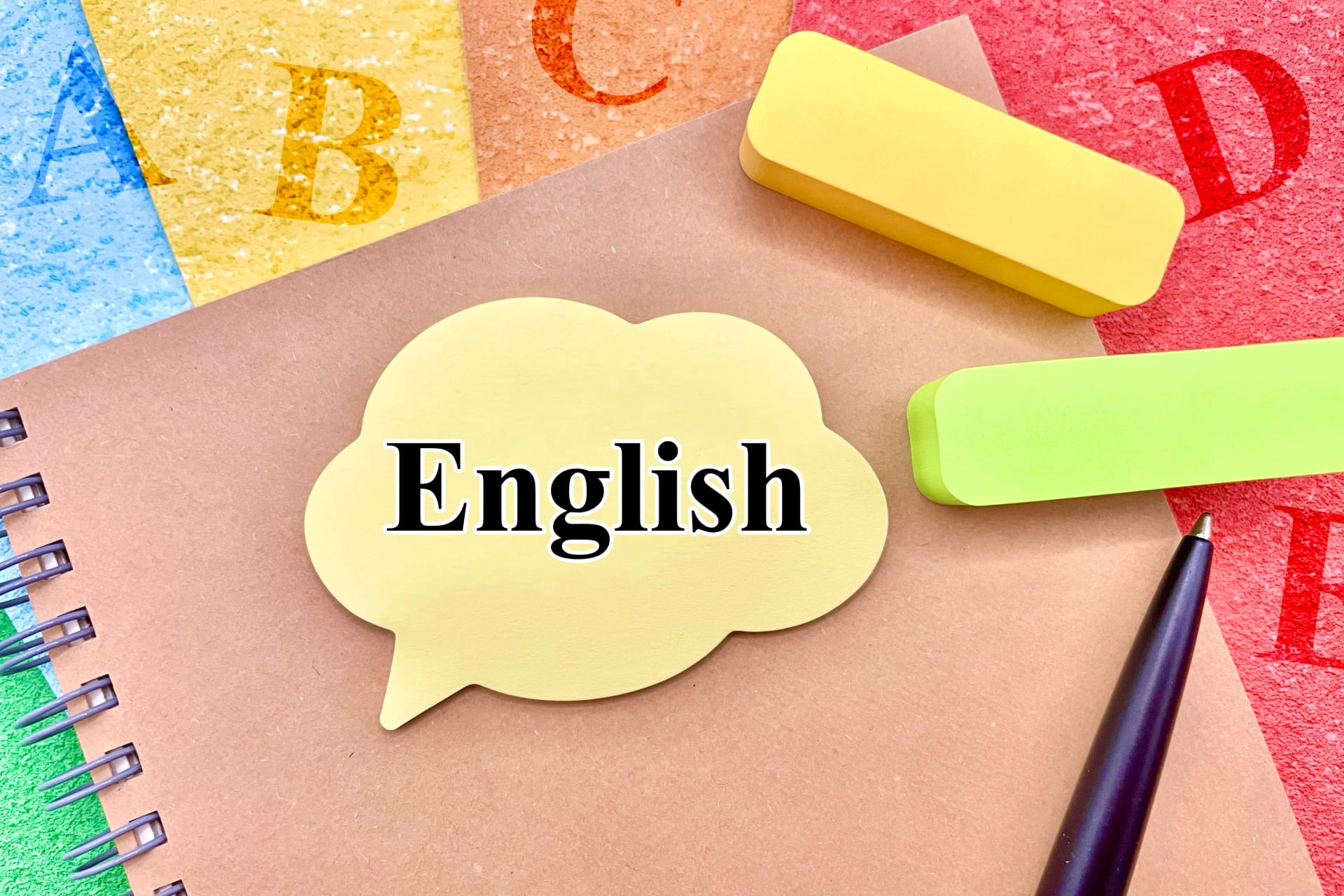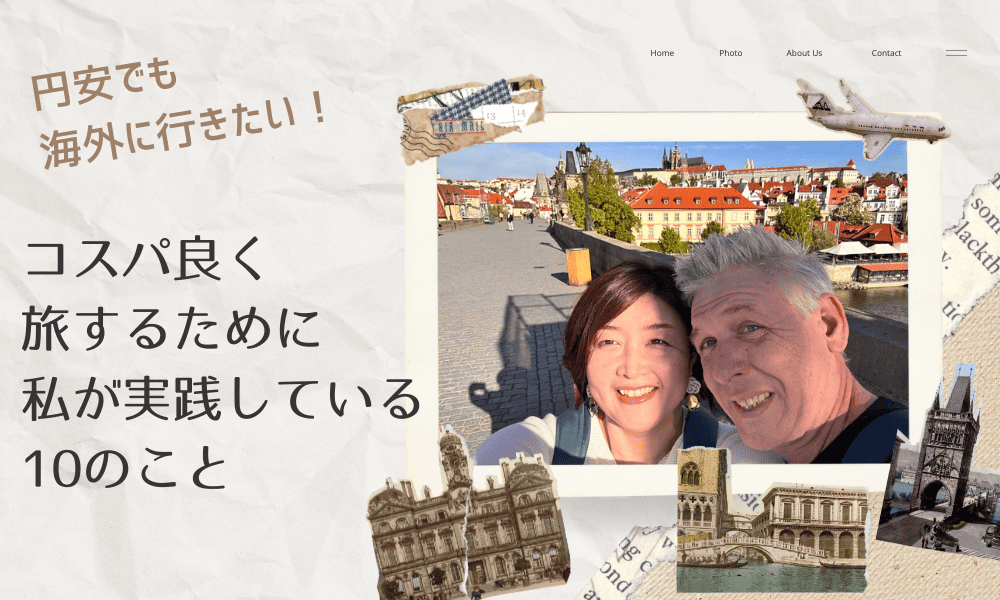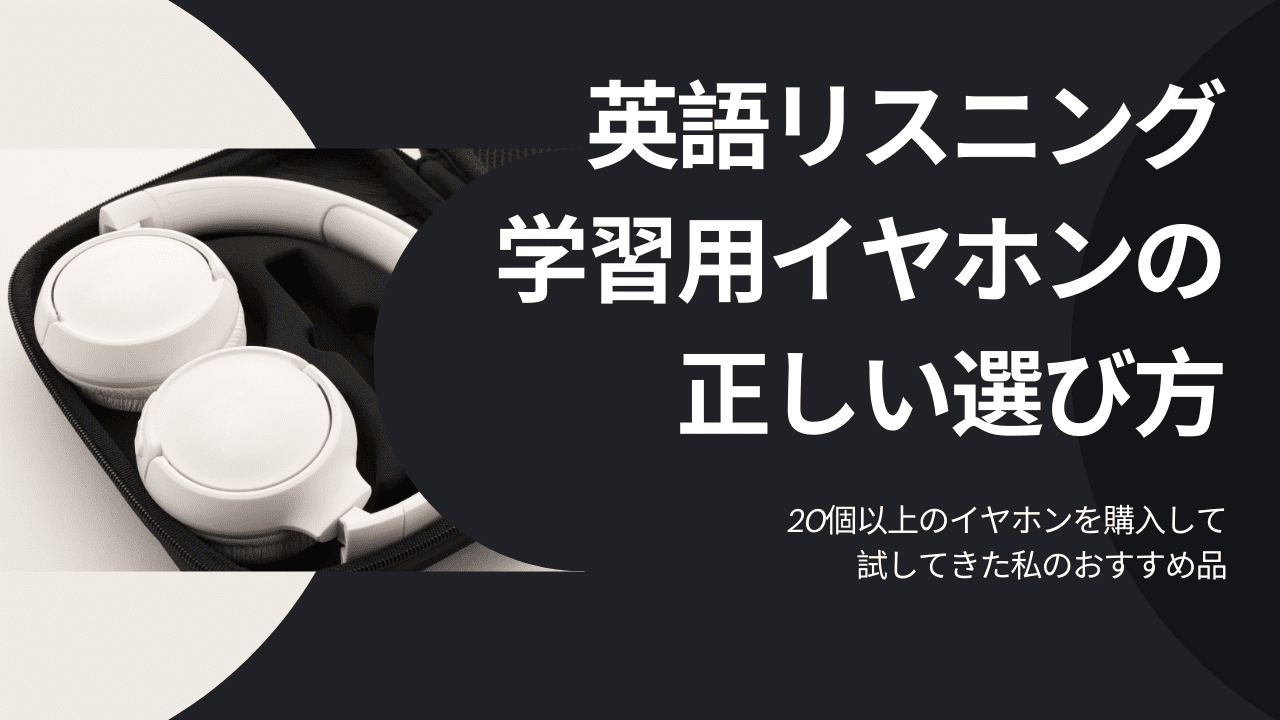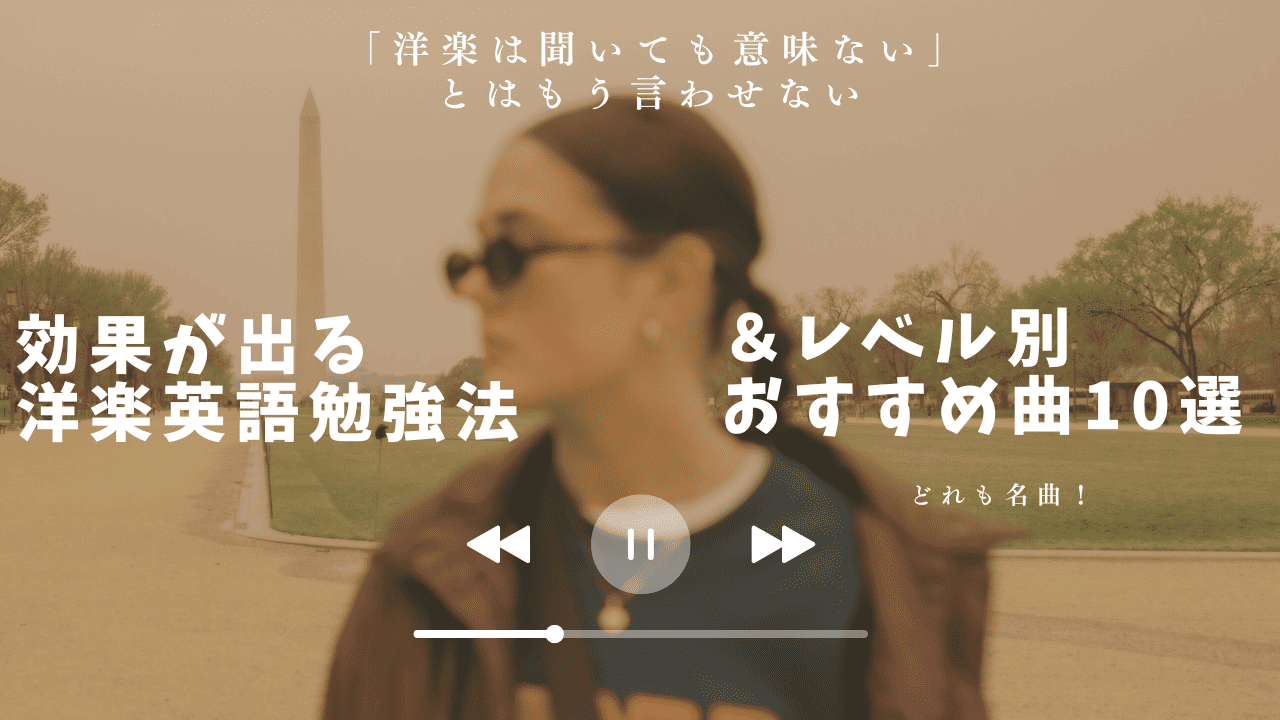2023年4月1日
生の英語がバッチリ聞き取れるようになるためのリスニング勉強法
 エバンス愛
エバンス愛
※当ブログ記事には、広告が含まれます。
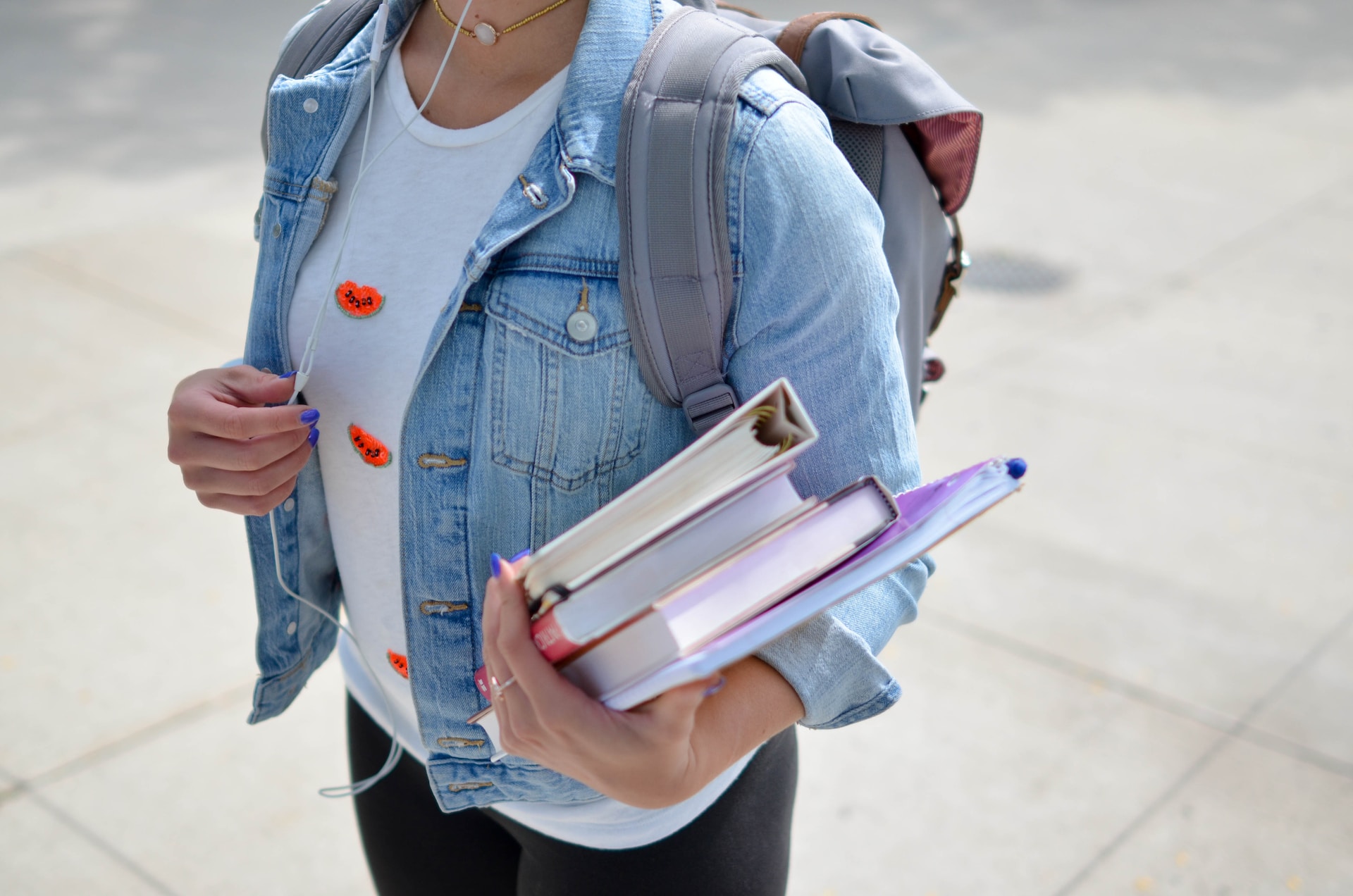

TOEICや英検の試験英語なら聞き取れるのに、
映画や海外ドラマの生の英語が聞き取れないのよね・・・
ネイティブと一対一なら、何とか言ってることも聞き取れるのに、
ネイティブ同士の容赦ないスピードの会話は全く聞き取れない・・・

こんな悩みを持っている人は、少なくないと思います。私も、長い間、生の英語が聞き取れないことに悩んでいました。
NHKのラジオ講座や英語教材は問題なく聞き取れるどころか、TOEICのリスニングセクションは満点なのに、映画やドラマの英語がほとんど聞き取れませんでした。
アメリカの夫の実家に行くと、アメリカ人家族が私に話しかけてくれる時の一対一の英語は理解できても、家族がお互いに英語で会話をしている時は、会話についていけませんでした。
私に突然話題が振られるたび、夫に「え?今何て?」と聞くのが恥ずかしくて、気まずい思いをしていました・・・
このページでは、「ネイティブの容赦ない生の英語が聞き取れない人が、どうすれば生の英語を聞き取れるようになるのか?」という話をしたいと思います。
読み終わる頃には、ネイティブの生の英語が聞き取れない理由と、その解決法が見えるようになっていれば幸いです。では、早速参りましょう!
コンテンツ
ネイティブの生の英語が聞き取れない3つの理由

教材やTOEICの英語なら聞き取れても、ネイティブの生の英語を聞き取るのが難しい理由を、3つ挙げます。
理由1.リエゾン(音がくっつく現象)が起きるから
英語には「リエゾン」と言って、前後の単語とくっついて違う音になるという現象があります。
具体的には、このように音がくっついて変化します。
How about you? →「ハウ アバウト ユー」「ハウバウチュー」
What if it rains? →「ワット イフ イット レインズ」「ワリフィッレインズ」
試験や教材用の英語でもリエゾン現象は起きるのですが、話し言葉では、試験や教材で使われるより正式な英語と比べると、このように音がグチャッとくっつく傾向が強くなります。
実は、日本語でもこの現象は起こっているんです。たとえば、話し言葉では「この間」→「こないだ」となったり、「置いておく」→「置いとく」となったりしますよね。
アナウンサーがニュースを読む時は、「こないだ」や「置いとく」なんていう言い方はしません。でも、私たちが普通に日常会話をする時は、こういう言い方をしますよね。
英語でも同じで、映画やネイティブ同士の会話では、音が連結するリエゾン現象が起こりやすくなります。だから、私たちには聞き取りが難しいわけです。
理由2.ネイティブは教材のような話し方はしないから
教材用にプロのナレーターがはっきりくっきり発音してくれた音源と比べると、私たち一般人の発音って、早口だったり不明瞭だったりしますよね。
映画でも同じです。映画の登場人物がアナウンサーみたいに滑舌良く発音していたら、逆に違和感ですよね^^;
私たち日本人が、家族や友達とのくだけた会話で、誰もアナウンサーみたいな話し方をしないのと同じように、ネイティブの普通の会話では、誰もTOEICのような話し方はしません。
だから、ネイティブのくだけた会話が理解できるようになりたいなら、くだけた英語で訓練をしないといけないんですね。
理由3.生の英語のリスニング訓練が足りないから
教材の英語なら何とかリスニングもできていたけど、「だいたい分かるから」と何となく今まで来てしまった人は、みんな生の英語で壁にぶち当たります。
「教材用の英語をたくさん聞いていたら、自然に映画の英語も聞き取れるようになる」ということは、残念ながらありません。訓練をしなければ、映画やネイティブ同士の英語は聞き取れるようにならないんです。
英語リスニングのレベルアップに行き詰った多くの人、特にがやりがちな勉強法は、「ただ何となく、海外ドラマなどで英語を聞く」ということです。
でも、しっかり目的意識を持って勉強していかないと、時間ばかりかかって成果が出ないので、それは避けたいところですね。
生の英語を聞き取る「精聴」と「多聴」リスニング勉強法

では、生の英語を聞き取れるようになるには、どうしたらいいのでしょうか?
それは、英語リスニングの勉強をするときに「精聴」と「多聴」という2つの異なるリスニング勉強法をバランス良く取り入れることです。
精聴と多聴は、車の両輪のようなものでどちらもリスニングの学習法に欠かすことができないからです。
まず、精聴と多聴の違いは、以下です。
精聴:一語一句すみずみまできっちり英語を聞き取る
多聴:一語一句にこだわらず、話されている内容をざっくりとらえる
両方必要なのですが、ほとんどの人は、「どっちか片方」しかやっていません。だから、英語が聞き取れるようにならないのですね。
ここから、精聴と多聴のそれぞれのポイントと勉強法をお伝えします。
精聴でリスニング力を上げる5つのポイント

まずは、精聴でリスニング力を上達させるための5つのポイントと勉強法についてお話していきます。
1.すべてを聞き取り、「だいたい分かる」で満足しない
生の英語が聞き取れないという人に一番よくありがちなのが、「単語は聞こえてくるし、だいたいの意味は分かるような気がするんだけど、それについて質問されたりとか、『じゃあ今の内容を要約して』とか言われると、途端に何も言えなくなってしまう」というパターンです。
これは結局、だいたい分かる気がしているだけで、実際は「分かってない」のです・・・。まず、その痛い事実を受け入れなければいけません。
「だいたい分かった気がする」で終わらせず、そこからもう一歩踏み込んでリスニング力を上達させるためには、この「すべてを聞き取る」という意識が重要です。
「すべてを聞き取る」訓練のための勉強法はいくつかあって、後で詳しく書きますが、最初は難しいことは考えずに、5分でもいいので「今話されている英語が全部聞き取れているか?」と集中して聞くことからはじめましょう。
2.特に最初は自分にとってやさしい英語を繰り返し聞く
いきなり、映画や海外ニュースなど難しい素材を使ってはいけません。最初は、自分にとって簡単なレベルの英語素材を使って、何度も繰り返して聞いてください。
私の場合は、TOEIC500点台から800点台くらいまでは、中学レベルや高校初級レベルの教材を聞きまくり、完全に一語一句聞き取れているという状態を意識して作りました。
TOEIC500点と言えば、「英語がまあまあ得意な大学生レベル」です。大学生レベルでも、中学生レベルや高校初級レベルの英語をめちゃくちゃ聞きました。
具体的には、初級英会話用のCD教材や、NHKのラジオ講座などをたくさん聞きました。
参考:私がNHKラジオ英語講座でTOEIC900超え(リスニング満点)した勉強法
3.脳内のカタカナ発音とのネイティブ発音のギャップを認識する
私たち日本人が英語リスニングで特に苦戦するのが、この「リエゾン」です。上でも述べましたが、リエゾンとは、前後の単語とくっついて音が変化する現象のことです。
ネイティブの英語を聞き取れなくしている障壁は、私たちの頭の中にある「この英語はこう発音するはず」という思い込みなんですよね。
たとえば、「I got it.」という英語を目で見ると、多くの日本人の頭の中では「アイ ゴット イット」というカタカナ英語が自動的に再生されてしまいます。
でも、ネイティブの実際の発音は(アメリカ英語では)「アイガリッ」なんです。
こういった、「自分の脳内で自動的に再生されるカタカナ英語」と「実際のネイティブ発音」の差を埋めていく意識で、英語をしっかり聞き取ることが重要です。
自分の脳内カタカナ発音とネイティブの発音のギャップを埋めるには、聞き取れなかった英語をスクリプトで確認する作業が不可欠です。
4.ディクテーションで自分のリスニング力の弱点を見つけ、強化する
本当に一語一句聞き取れているかどうかを簡単に確認できるのが、ディクテーションという勉強法です。
ディクテーションとは、何も見ないで英語の音声だけを流し、音声を適度に止めながら聞こえた英語を書き取っていくという学習法です。
参考:ディクテーションで英語力に革命が起きる!効果と正しいやり方を徹底解説
音声を何度か巻き戻しながら、もうこれ以上は聞き取れないという状態になるまで繰り返し聞いて、聞き取れなかった部分を埋めていきます。そして、最後にスクリプトを確認して答え合わせをします。
ディクテーションを行うことで、自分の弱点(聞き取れなかった部分)がはっきりします。
単語を知らなかったからなのか、音がくっついて変化していたからなのか、きちんと聞き取れなかった原因を必ず確認することを忘れないようにしてください。
スクリプトの英語を確認した時に、「なんでこんな簡単な英語が聞き取れなかったんだろう?」と思ったら、リスニング力アップのチャンス。
聞き取れなかった原因は、リエゾンなど音の変化に耳が慣れていないか、あるいは単語の発音を間違って覚えているかのどちらかです。聞こえなかった原因をきちんと探り、その箇所を重点的に復習してくださいね。
5.シャドーイングでリエゾンやイントネーションを身につける
シャドーイングとは、英語音声を流しながら、その直後を影のようにくっついて発音を真似て発声していくというトレーニング法です。
何も見ないで聞こえた音だけを頼りに英語を発音していくので、英語が一語一句聞き取れないとできない勉強法です。
参考:シャドーイングを5年続けて通訳になった私のやり方と継続のコツ
シャドーイングをする時に重要な点は、「自分の脳内のカタカナ英語は捨てて、聞こえた通りに忠実に真似をする」ということです。
細かい音(vとかfとか)を正確に発音するというよりは、そっくりそのまま真似することに重点を置いてください。イントネーションとは、文章全体でどこが強くゆっくり読まれ、どこが弱く速く読まれるかということです。
一つ一つの単語にこだわって発音しようとするとイントネーションが疎かになってしまうので、細かい発音より全体のリズムを意識して雰囲気をそっくり真似するよう心がけてくださいね。
多聴でリスニング力を上げる5つのポイント

次は、多聴でリスニング力を上達させるための5つのポイントと勉強法についてお話していきます。
1.一語一句にこだわらず、大まかな意味をとらえる
精聴とは対照的に、多聴は「細かいところは置いておいて、意味をざっくりとらえる」ことに注力します。
上記でお伝えした「一語一句漏らさず聞き取る」という精聴も重要なのですが、それだけに慣れてしまうと、今度は「聞き取れないところが気になって、次の英語が聞こえなくなってしまう」という悩みにぶち当たります。(汗)
特に映画やネイティブの生の英会話は、すごいスピードで情報が流れてきますから、一語一句聞き取ろうとすると脳の情報処理が追いつきませんよね。
なので、全ての単語が聞き取れなくても、聞き取れた部分をつなぎ合わせてざっくりと意味を理解するという訓練が重要になります。
2.自分にとって難しめの英語を5W1Hに注意して聞く
「大まかに意味をとらえる」多聴素材の選び方のポイントは、自分にとってちょっと難しいと感じるものを選ぶことです。
これは、一語一句聞き取れるものをたくさん聞いてシャドーイングばかりしていたせいで、「細かいところは気にせず全体を大まかに理解する」ができるようになるのにすごくすごく苦労した私の苦い経験からも、強く意識して欲しいと思う点です。
一語一句は聞き取れなくても、「誰が・どうした(+いつ・どこで・なぜ・どのように)」の5W1Hを理解できたらとりあえずOKというつもりで、完璧を目指さず取り組んでください。
使う素材はお手持ちのものでいいですが、あまり長くなく、スクリプトで後で英語が文字で確認できるものにしてください。
たとえば、私が講師を務めているリーディング教材の長文には、ネイティブ音声がついています。まずは長文を読む前に、5W1Hに注目して音声だけを聞いてみて、どれほど理解できるかをやってみてください。
3.聞きっぱなしにせず、スクリプトで単語や熟語を確認する
多聴では「一語一句が分からずとも、だいたい理解できたらそれでいい」という取り組み方をするのですが、「だいたい理解できた」で終わらせてはいけません。
そこで終わらせると、いつまでも「だいたい分かる」から抜け出せなくなり、リスニング力がいつまでたっても伸びないという状態に陥るからです。
多聴をする時の最初の目的は「全体を大まかにつかむ」でいいのですが、全体をざっくり理解するという段階が終わったら、そのスクリプトを確認して聞き取れなかったところ、意味を誤解していたところなどをチェックしてください。
おそらく、知らない単語や熟語もあるはずなので、ざっと確認して、またその素材を何度も聞き直してください。
最終的には、多聴で使った素材を、きちんと意味や新しく学んだ単語を確認した後に何度もながら聞きで復習して意味や単語を定着させ、最後にはシャドーイングやディクテーションなど精聴で再利用すると理想的です!
英語リーディング教材SPEEDIER READINGは、そんな使い方にも適しています。他に適当な教材をお持ちでなければ、検討してみてくださいね。
4.意味の分からない英語を漫然と聞き流すのはやめる
「英語のシャワーを浴び続ければ、いずれ英語が自然に聞き取れるようになる」というのは、嘘です。聞き取れないものをただ流し続けても、聞き取れるようにはなりません。
よく、CNNを家でつけっぱなしにしているという人がいますが、TOEIC900点台以上の上級者以外には意味がない勉強法なので、辞めましょう。
参考:英語のシャワーはなぜ危険?そのリスニング勉強法は効果ナシです
中国語を全く理解できないあなたが、中国語のニュースを毎日テレビで流しっぱなしにしていたら、そのうち中国語が理解できるようになるでしょうか? なりませんよね。
聞き取れないのには原因があって、その原因が解消されなければ、聞き取れるようにはならないんです。
参考:【英語の聞き流し】効果があるのかないのか、白黒つけようじゃないの
知らない単語があるから聞き取れないのなら、その単語の意味をまずは知らなければ理解できないですよね。知らない単語の音を何度繰り返して聞いたって、知らない単語は知らない単語のままです。
聞き取れなかったところを聞き直し、なぜ聞き取れなかったか原因を確認し(単語を知らなかったのか、音の変化で聞こえなかったのか、など)、その原因に注意してさらに聞き込むという作業を繰り返す。
それをしないと、今まで聞こえなかった英語が聞こえるようになることはありません。
5.海外ドラマを使って英語を聞く訓練をする
そして最後は、実際に「容赦ないネイティブの弾丸スピード英語」で、英語を聞き取る訓練をしていきましょう。
使う素材は、訛りが強くなく、専門用語の多くない海外ドラマをお勧めします。『フレンズ』などが有名ですが、自分が好きなドラマで構いません。私が好きなドラマは、NYの弁護士事務所を描いたドラマ『SUITS』です。
ドラマのワンシーンで良いので、まずは字幕なしで音声だけでどれだけ聞き取れるかを試してみてください。そして、次は英語字幕ありで見て、知らない単語や表現があったら辞書で調べて確認します。日本語字幕つきで意味を確認したら、もう一度、字幕なしで見てみてください。
長いシーンだと疲れるので、最初は5分ほどの短いシーンで大丈夫です。可能なら、登場人物の英語を真似て発音してみるとさらに効果がアップします。
使うドラマは英語字幕が必要ですが、ほとんどの洋画や海外ドラマに英語字幕がついているNETFLIXが、一番使い勝手がいいと思います。amazon primeの場合は、「AMAZON ORIGINAL」と書いてある作品なら、だいたい英語字幕があるはず。
参考:海外ドラマで効果的にリスニング力と英会話力を伸ばす5ステップ学習法
生の英語が聞き取れるようになる勉強法・まとめ
というわけで、生の英語が聞き取れるようになるためのリスニング勉強法をお話ししましたが、いかがだったでしょうか?
まずは、一語一句聞き取る「精聴」を、以下のように取り組む。
1.すべてを聞き取り、「だいたい分かる」で満足しない
2.特に最初は自分にとってやさしい英語を繰り返し聞く
3.脳内のカタカナ発音とのネイティブ発音のギャップを認識する
4.ディクテーションで自分のリスニング力の弱点を見つけ、強化する
5.シャドーイングでリエゾンやイントネーションを身につける
そして次は、大まかに全体像を理解する「多聴」を、以下のように取り組む。
1.一語一句にこだわらず、大まかな意味をとらえる
2.自分にとって難しめの英語を5W1Hに注意して聞く
3.聞きっぱなしにせず、スクリプトで単語や熟語を確認する
4.意味の分からない英語を漫然と聞き流すのはやめる
5.海外ドラマを使って英語を聞く訓練をする
私は、多聴に正しい方法で取り組むのが遅れたせいで「TOEICのリスニングは満点なのに、映画もニュースも全然ダメ」という屈辱的な状況を長く味わいました。生の英語が聞けないことがコンプレックスで履歴書にTOEIC980点と書くのが本当に嫌でした。
今、TOEICの点数が伸び悩んでいる方は、「980点もあるのに自信持って書けないの?意味がわからない!」そう思うかもしれません。
でも、もしあなたが私と同じように「試験の英語なら聞き取れるのに、実践的な英語力に全然自信がない」という場合、私の気持ちは分かっていただけると思います。
私が、「生の英語が聞き取れない」という状態から抜け出したきっかけが、多聴と精聴にバランス良く取り組むようになったことなのです。
それまで間違ったリスニングの勉強をしていた私が、今では映画も海外ドラマも字幕なしで観るし、夫と一緒のタイミングで笑えるようになり、通訳として働くようになりました。
なので、ぜひあなたも諦めずに、正しいやり方でリスニングの勉強を続けていってくださいね。
このページの内容が、あなたのリスニング力アップのお役に立てれば幸いです!最後までお読みいただき、ありがとうございました。
多くの人は、英語が「聞き取れない」に加えて、「しゃべれない」というお悩みも抱えていらっしゃると思います。このページもよかったら読んでみてください。
▶日本人が英語が苦手な本当の理由【10年も勉強したのにしゃべれない問題】