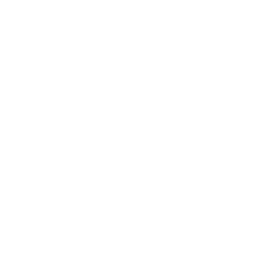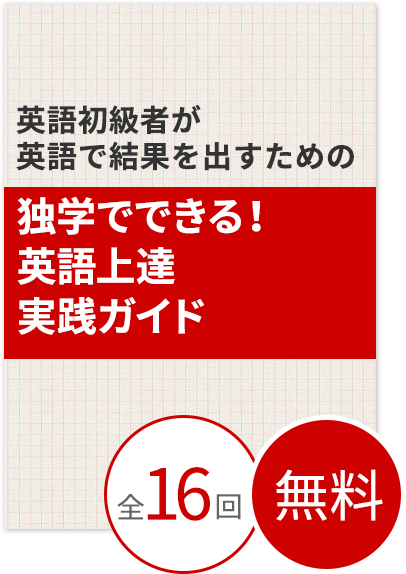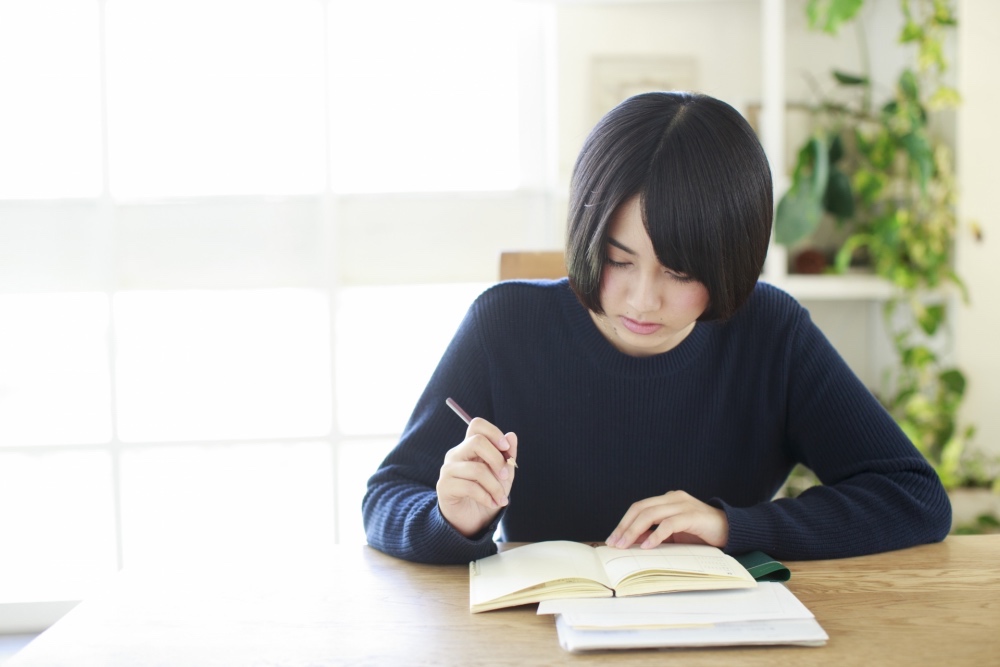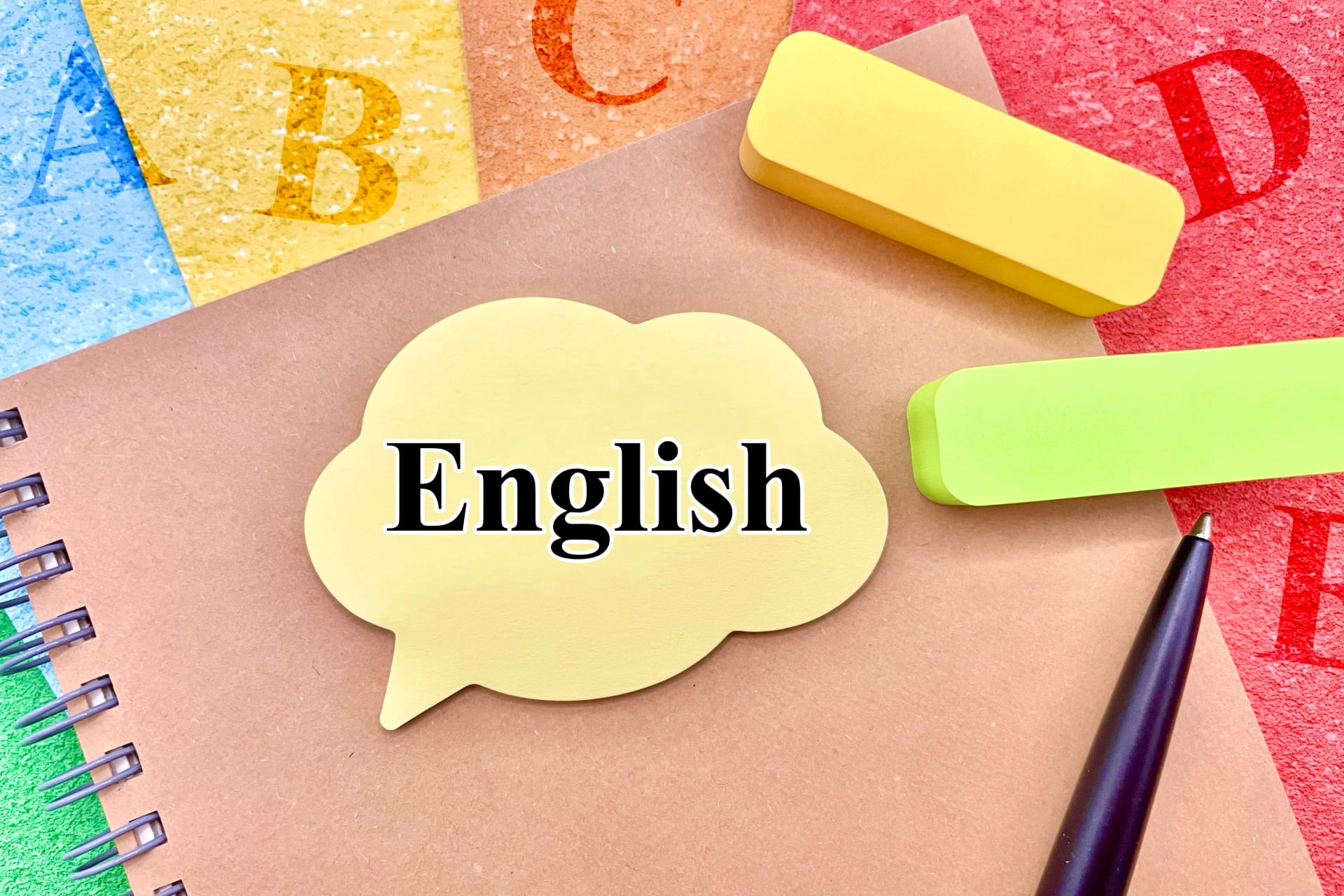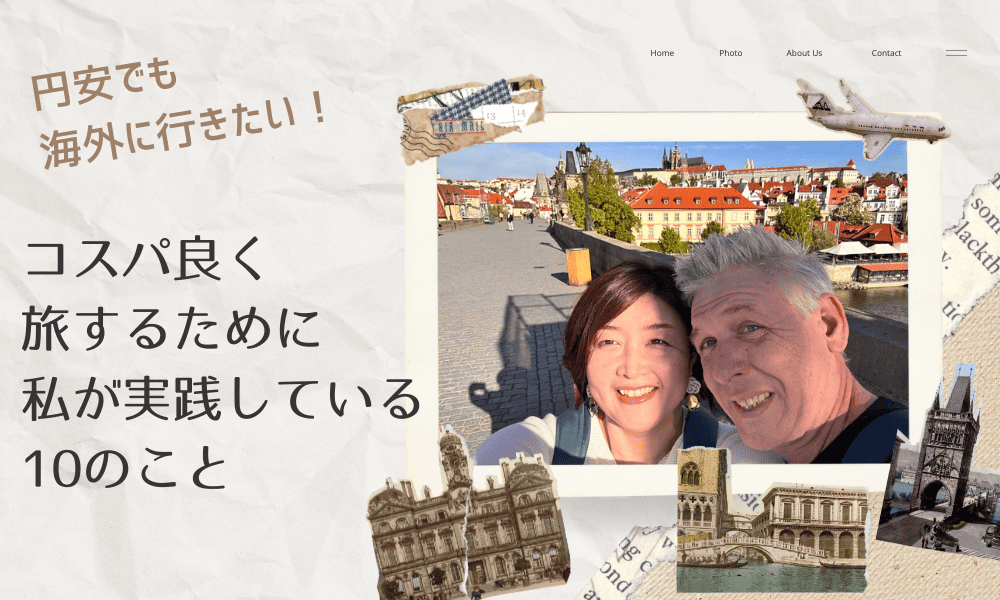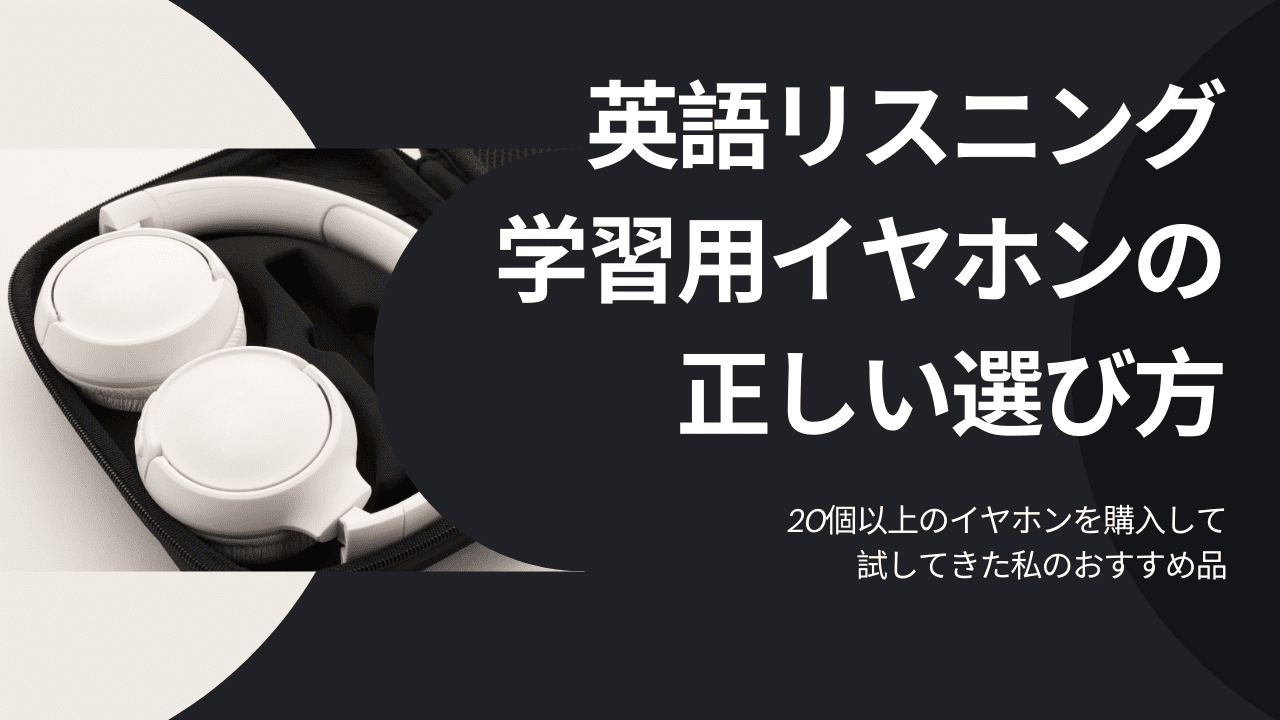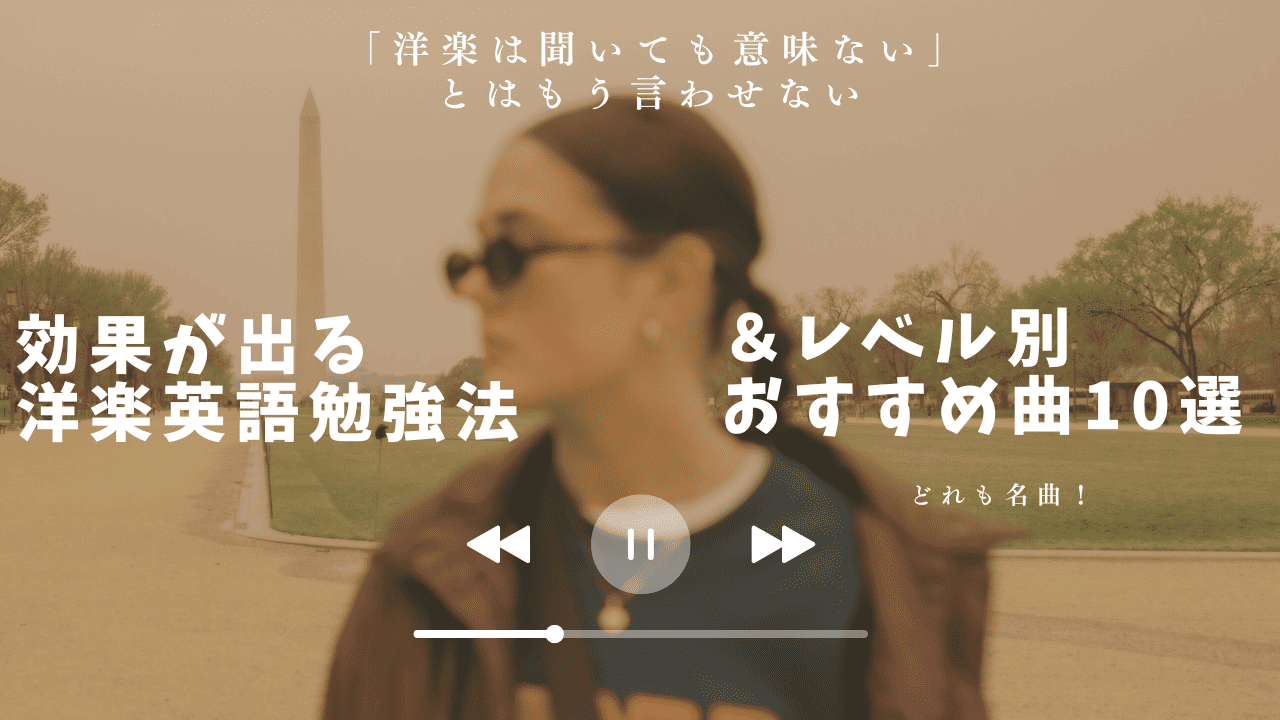2023年2月27日
翻訳者歴12年の私が考えてみた、翻訳者になるための10の条件
 エバンス愛
エバンス愛
※当ブログ記事には、広告が含まれます。

「翻訳者になりたいと思って勉強しています」「どうしたら翻訳家になれますか?」というメールをよくいただきます。
自宅で仕事ができるし、憧れる人が多い職業だと思いますが、身近に翻訳者がいないとなかなか実態がわかりづらいですよね。
そこで、翻訳という仕事をするのに必要な10の条件ということで、現役の在宅翻訳者さんの話も交えつつ、翻訳の仕事を12年やってきた私の考えをお話ししたいと思います。
今後翻訳者を目指す方、副業で在宅翻訳をしたい方にはとても役立つ情報だと思います!
コンテンツ
翻訳者になるための10の条件
1.翻訳者に必要な英語力は英検準1級、TOEIC900点
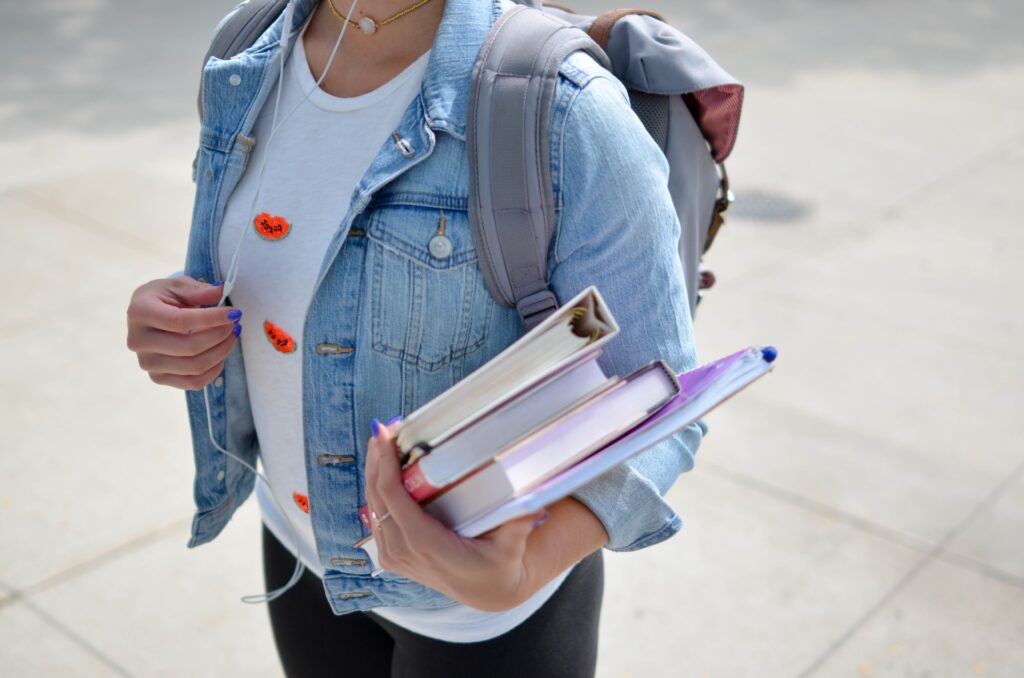
「翻訳者になるには英検準1級、TOEIC900点程度が必要」と、在宅翻訳者を目指す人向けのセミナーで聞いたことがあります。
私の感覚では、「英検準1級に合格した」というだけでは心もとないと思います。なのであえて言うなら、準1級に「余裕で」合格できる程度。または英検1級の1次試験合格程度だと安心です。
英会話が苦手で2次試験に苦戦する人でも、1次は合格するくらいの読解力やライティング力はあった方がいいと思います。(理系の専門知識などがある場合は、必ずしも英語力がそこまで高くない場合もあります)
ただし、その在宅翻訳者志望者向けセミナーでは、英検準1級、TOEIC900点というのは「それ以下だと足切りされる」という意味での基準だと言っていました。つまり、スタートライン。
この基準に達してなくてはダメというわけではありませんが、達したからといって自動的に翻訳者になれるわけではありません。TOEIC900も英検準1級も、「ないよりはあった方がまし」という程度です。
「翻訳者になりたいからTOEIC900点を目指します」「英検1級に合格したら翻訳の勉強を始めます」というのは、ナンセンスです。
こういう人めっちゃ多いんですが、私はこの症状を「もう少し勉強してから病」と呼んでいます。(苦笑)
以下のページに詳しく書いているので、よかったら読んでみてください。
▶通訳翻訳に英検1級は有利?「もう少し勉強してから」は禁句にしよう
2.自分の強みの分析(できれば英語以外の強み)

私が知る在宅翻訳者で、コンスタントに仕事が受注できていて、収入も多くて成功している男性翻訳者は、「英語が得意だから」翻訳を仕事にしたのではなく、大学の専攻(理学部)、就職した企業の業種での経験が売りにできると考えて、在宅翻訳の道に進んだそうです。
彼は英語レベルも高かったのは間違いないですが、英語以外の強みを分析できていて、それをアピールしたことが勝因だと思います。
翻訳者を目指すなら、英語ができるのは当たり前で、それだけで「売り」にはならないです。
よく、「私は英語専攻ではないのですが、やはり翻訳の仕事は厳しいでしょうか?」というメールを翻訳者志望の人からいただきますが、英文科・英語科卒でなくて全く問題ありません。
むしろ、英語以外の専攻の方がいいくらいです。特に科学系、技術系などのバックグラウンドを持つ人は、翻訳には有利です。英語の産業翻訳が発生する業界のほとんどが、製造業や医薬、化学など理系分野だからです。
「英語が得意だから翻訳をする」でもいいし、多くの翻訳者は最初はそうだと思うのですが、英語ができるのは当たり前で、それ以外に自分の得意分野、専門分野を見つけることがやっぱり大事だなと思っています。
この記事が参考になるかもしれません。
▶初心者から翻訳家になれますか?ゼロからデビューまでの最短ルート
3.翻訳の仕事の半分以上はリサーチであることを受け入れる
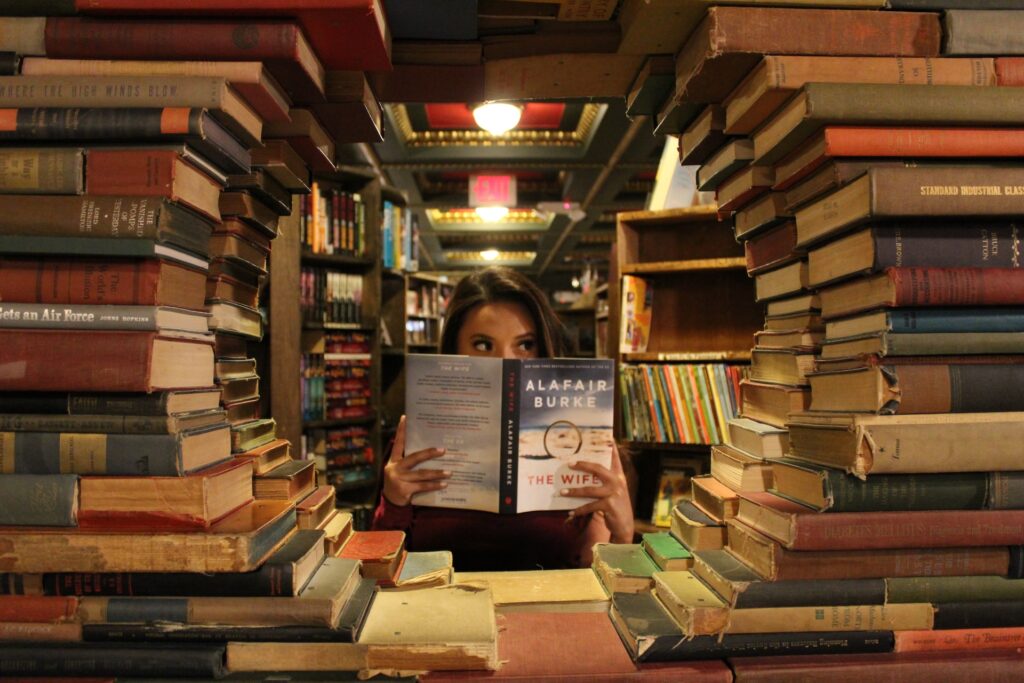
「英語が好き」では、翻訳はできません。
翻訳という仕事の7割くらいは、実は文献を調べて知識を得たり、自分の考えた訳語が本当にその業界で適切な言葉かという調査です。つまり、英語を日本語に、日本語を英語にするという作業以外の仕事です。
私は翻訳エージェントとして仕事を受注して、翻訳経験のない、または浅い人に下訳(正式な翻訳文書の下書きを作る作業)をやってもらったりしています。その仕事ぶりを見てきて痛感しているのは、「調査能力」がものすごく重要だということと、それを甘く見ている人が多いということです。
参考書籍、ネットの情報(英語含む)、人脈などを使って、いかに欲しい情報を早く正確に得るか?というスキルが劣っている人は、いくら英語力を磨いても厳しいです。
どうすれば調査能力が上がるかというと、これは経験しかないです。あとは、最適の訳語が見つかるまでとことん調べるのだという「意志」です。「ここは調べたら簡単に分かるでしょ?」ということをちゃんと調べてない場合、残念ながら意志や自覚が欠けていると言わざるを得ません。
あと、何でもネットの日本語検索だけで済ませて「リサーチは十分した」というのも、大いなる勘違いです。英語の文献やホームページにもあたるのはもちろん、必要ならGoogle翻訳を使ってフランス語やドイツ語の情報を得たりすることもあります。
4.言葉に対する敏感さ

私自身もまだまだ修行が足りないのですが、「本当にこの日本語(英語)でいいか?」ととことん考える姿勢が大事です。
普段から句読点の使い方、「ら抜き言葉」など間違った言葉、主語と述語の呼応など、いろんな文章を読みながらの気づきの時間すべてが翻訳の勉強です。
言葉にこだわりつつ、丁寧に、でもスピーディーに仕事をするのが大事です。そのためには、普段から言葉への感性を磨こうと努力する姿勢が大事なのかなと思います。
ちなみに、「翻訳が上手ですね」ではなく、「え?これ翻訳なの?原語かと思った」が翻訳者が最も喜ぶべき褒め言葉だ、と経験豊富な在宅翻訳者の方が言っていました。(※ただし、依頼主、内容によっては直訳調が好まれる場合もあるので、一概には言えませんが)
とはいえ、翻訳の良し悪しを決めるのはユーザーなので、翻訳者の自己満足で仕事をしてはいけません。その文章を誰がどういう目的で読むのかということをしっかり意識して、それに最も適した文体で翻訳を完成させることが求められます。
5.ITスキル

翻訳って文系の仕事のイメージなので、あんまりITスキルが必要というイメージがわかないかもしれませんが、ITに強いこと(少なくとも強くあろうとすること)がめちゃくちゃ重要です。
特に、在宅で翻訳の仕事をして普通に会社勤めレベルの月収を得ようと思うと、それはもう、ものすごいスピードで翻訳することが必要です。翻訳に加えて、上でも言ったように、リサーチにも大量に時間が取られます。
機械の力を借りて翻訳をすることは、翻訳者にとって必須です。たとえば機械翻訳や翻訳支援ツール、置換、ワイルドカード、マクロなどです。
「私は今までこうやってきたから」と過去のやり方に固執するのではなく、新しい技術について積極的に情報収集をして、常に「もっと速く品質の良い仕事を仕上げられる方法はないか」と、改善する方法を模索する姿勢が大切です。
私が、「稼いでいる在宅翻訳者はここまでするのか!」と衝撃を受けて大いに参考にさせてもらった、ITスキルを使いこなしている翻訳者さんの本をご紹介します。この本で紹介されているワイルドカードは、普段の文書作成でもすごく使えます。
「語学力ゼロで翻訳できる」というのは出版社さんの考えた売り文句だと思いますが、「結局、語学力よりITスキルなんだな」ということが分かると思います。
6.不特定多数の人が読むことを前提に文章を書く習慣

英日翻訳では、日本語力が本当に重要です。なので、日本語能力も磨き続ける必要があります。
「人に読ませるための日本語を書く」トレーニングとして有効なのは、ブログを書くことかなと思います。不特定多数の人が読むことを前提にブログ記事を書いてトレーニングするのは、とてもいい練習になります。
まあ、こうして私も日々ブログやメルマガを書いて、文章力を高める練習をしているんだ・・・とお思いかもしれませんが、実はそんなことを考えたこともありませんでした。でも、今となってはこの積み重ねがすごく役に立っていると思います。
このブログも、翻訳のトレーニングのつもりなら、もっとマシな日本語を書かなくちゃいけませんが、私もその気になればまともな日本語だって書けるんですよ。←まるで説得力なし。(;・∀・)
7.日本語の論理的思考力、理解力

あなたがもしも文芸翻訳を志しているなら、当然ですが、その原書の雰囲気に合う格調高い文章や読者を引きつける魅力的な文章が書けることが必要です。
この記事は、主に産業翻訳を想定して書いているのですが、産業翻訳にも日本語能力は重要です。
私たち日本人の思考は、日本語で行われます。つまり、論理的に考えたり、難しいことを理解する力は、私たちの日本語能力に依存します。翻訳は、ただ英語と日本語を入れ替えるのでは不十分で、訳者がその内容を理解していることが重要です。翻訳した文章を見れば、訳者が理解できているのかそうでないのか、すぐ分かります。
というわけで、論理的思考力や理解力が重要なので、母国語である日本語力が大事ということです。
ちなみに、「翻訳者になるには高い英語力が必要だから、ボキャブラリーが重要。たくさん単語を知っておかないといけない」と思う人が多いですが、これは勘違いです。知らない単語なんて、辞書を引けば済むからです。
たくさんの英単語を知るよりずっと大事なのは、思考力を身につけることです。一朝一夕に身につくものではないので、日頃の読書や日本語でのアウトプットを通じて、継続した訓練が必要です。
8.安定して生活と仕事を継続できる基盤

在宅翻訳だったらどこに住んでいてもできるから、今流行りのノマド生活で、世界各地を転々としながら翻訳生活だってできそうですよね。
あるいは、物価が日本の数分の一の海外に移住して在宅翻訳で生計が立てられたら、生活費も数分の一で済むし、翻訳料が少々安くても十分生きていけるのでは?と憧れる人は少なくないと思いますが、現実はなかなか甘くはないようです。
在宅翻訳は基本的にそれまでの信頼関係で仕事が継続するものです。「旅行に行くので、その時期は納品が遅れます」みたいなことがあるようだと、別の翻訳者に仕事が渡ることになってしまいます。
安定して収入を得るためには安定して仕事を受け続けるしかないわけで、そうなると「旅をしながら翻訳生活」は現実的には厳しいかもしれません。
パソコン片手に旅先で翻訳しながら・・・なんて生活、優雅で憧れます。でも、実際はせっかく旅先にいても、きれいな景色を満喫する暇も全くなくホテルの部屋にこもりっきりで翻訳しないといけないなら、意味ないですよね。
私自身は、在宅翻訳の案件を持ったままアメリカに休暇に出かけた時は、飛行機の中や空港で乗り継ぎの待ち時間に翻訳作業をし、スタッフや依頼主とはアメリカからメールでやりとりをしました。
とはいえ、飛行機の中ではオンライン辞書が使えず不便だったり、旅先では時差ぼけや観光疲れで作業時間が確保できなかったり、調整が難しかったです。旅行中の翻訳も、たまにだったらいいですが、恒常的には続けるのは難しいと自分の経験からも感じました。
せっかくどこにいても仕事ができるフリーランス翻訳者ですが、普段の在宅翻訳の作業は、やっぱり自宅で落ち着いてやると一番いい仕事ができます。(笑)
9.「○○になったら翻訳の勉強を始めよう」で逃げない勇気
今はまだTOEICが500点とか、英語の勉強のやり直しを始めたばかりの人とかなら、まずは基礎固めをしてとりあえずTOEIC700点を目指そうか、という考え方でいいです。
でも、すでにTOEIC800点とか900点とかの人が、「英検1級を取ったら翻訳の勉強を始めようと思っています」とか、「翻訳の仕事をしたいですが、まずはTOEICでもっと納得できる点数を目指しています」と言っているのを頻繁に耳にします。
痛いとこを突きますが、「勇気がないから、まだ翻訳の世界に踏み出したくありません」が、その人たちの本音かもしれません。でも、TOEIC800点とか900点レベルの人は、もう英検とかTOEICとかどうでもいいので、今すぐ翻訳に関わる何かを始めたほうがいいです。
今すぐ翻訳の仕事に応募しなくても、まずは翻訳コンテストに挑戦してみるとか、翻訳学校の資料請求をしてみるとか、翻訳セミナーに参加してみるとか、とにかく翻訳という仕事がもっと現実味を帯びて感じられる距離感に近づくことが重要です。
翻訳の仕事に直結する一歩を踏み出してください。以下の記事に掲載しているような、翻訳コンテストに挑戦されるのもいいと思います。
▶翻訳コンテスト情報まとめ!気軽な英語の力試しに【2023年5月最新版】
さっき「翻訳者になるならTOEIC900点と英検1級の1次試験合格程度」って言ったのに、矛盾してる!と思うかもしれませんが、翻訳の勉強を真剣にやって、お金がもらえるほどのスキルが身についたら、TOEIC900点と英検1級の1次試験合格くらい勝手に到達してます。
決して、TOEIC900点と英検1級のために試験勉強をして、そこを越えたら翻訳の勉強を始めましょうという意味ではありません。
実際、英検1級の方でも翻訳をやらせたら微妙な方もたくさんいれば、1級を持ってなくても上手に翻訳が出来る方もたくさんいます。翻訳者になるための特別な勉強って、ないと思います。実践することでしか上手にならないんですよ。
10.結局は意欲
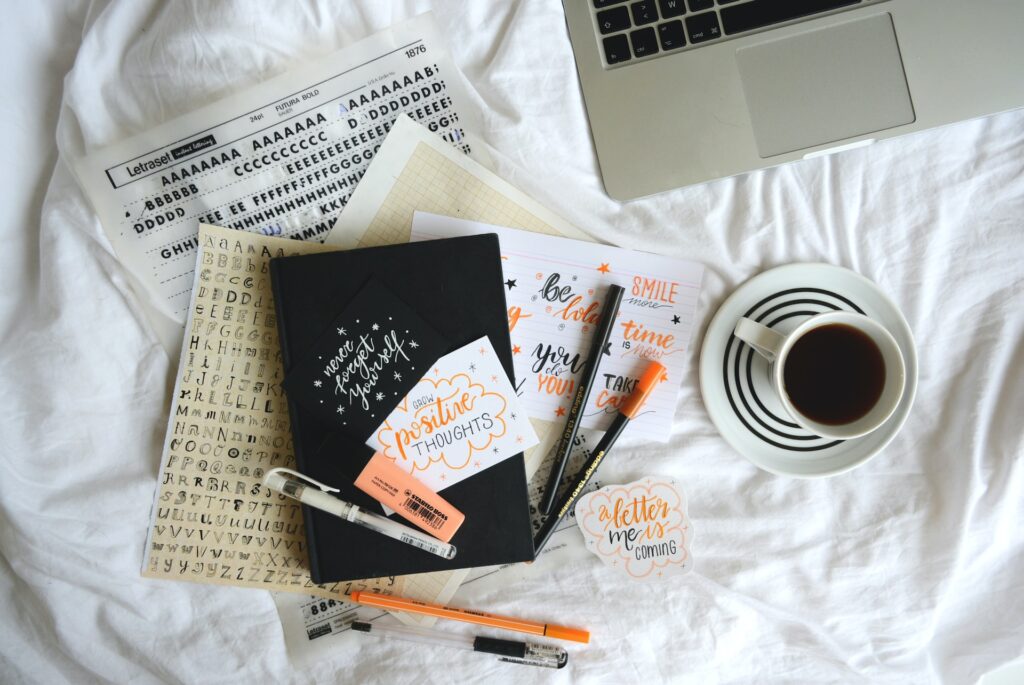
どうしても翻訳を仕事にしたいんだ!という強い意欲が重要。当たり前のようで、ここがぼやっとしている人がとても多いのではないかなと感じています。
もちろん、これを読んでくださっている方は誰もが「翻訳者になりたい」とお思いのはずですが、その思いがどれほど強いかということです。
正直に言うと、「翻訳者になりたい」と言っている方の半分くらいは、「なんとなくカッコいい」「家で働けるし良さそう」くらいの憧れの気持ち程度でそう言っているように思います。
しっかり情報収集をして、経験者の話を聞いて、翻訳に直結する勉強をして、トライアルや求人に応募することを通じて、より翻訳という仕事を現実的に意識してください。そして、「自分は絶対に翻訳者になりたいんだ!いや、なるんだ!」と気持ちを高めていってください。
もちろん、「なんか自分のイメージと違ったな」と思って諦めることになるかもしれません。でも、それも実際に行動に起こしたから気づけるわけで、現実を知らないで「翻訳者になりたいな〜」という憧れで時間を無駄にするよりは、ずっといいですよね。
ところで、以前私のところで在宅翻訳をしてくれるスタッフを募集したとき、強い意欲が感じられる応募者さんが少なくて驚きました。それも、自己アピール欄にわざわざ「しっかり書いてください」って注意書きしてあるのに、です。
相手が欲しがる圧倒的な経験やスキルがあるなら別ですが、そうじゃないのに、ここで意欲の強さを出さなくてどうする!と、私は応募書類を見ながらもったいなく思いました。
翻訳者になるための条件まとめ
以上、私の独断と偏見で、翻訳者になるための条件をまとめてみました。
1 翻訳者に必要な英語力は英検準1級、TOEIC900点
2 自分は何を売りにできるのか?の分析
3 翻訳の仕事の半分以上はリサーチであることを受け入れる
4 言葉に対する敏感さ
5 ITスキル
6 不特定多数の人が読むことを前提に文章を書く習慣
7 日本語の論理思考力、理解力
8 安定して生活と仕事を継続できる基盤
9 「○○になったら翻訳の勉強を始めよう」で逃げない勇気
10 結局は意欲
というわけで、いかがだったでしょうか?
あくまでも私の個人的な経験に基づく考えなので、翻訳者さんによっては全然違う項目になると思います。それでも、例えば「ITスキル」なんかは、どの翻訳者さんも必須だとおっしゃるはずです。
このページで挙げた内容で、ひとつでもピンと来るものがあれば、ぜひ翻訳者を目指すために取り入れていただけたら幸いです。
翻訳者の仕事の内容や収入、私が翻訳者になった経緯などにご興味があれば、こちらも合わせてどうぞ。
▶翻訳者への道ー私が未経験から翻訳の仕事をゲットして転職した方法