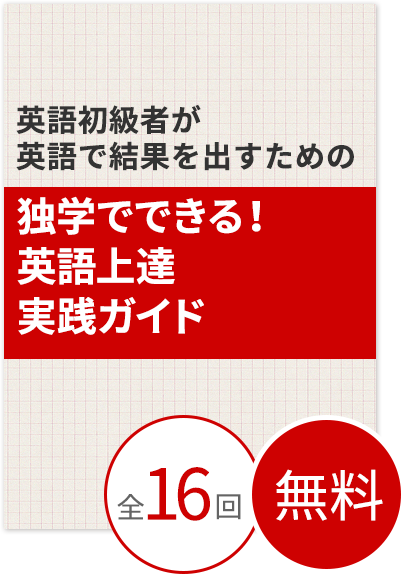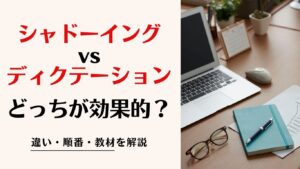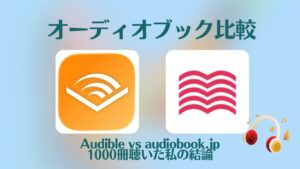英語のリスニングが伸びるコツ|通訳が教える、「聞く」力の育て方


一つでも聞き取れない単語があると、そこが気になって続きが頭に入らなくなる・・・

スクリプトを読みながら英語を聞いても、どうしても聞き取れない音がある・・・
このように悩んで、リスニングのやり方に自信が持てないという方は多いのではないでしょうか?
実は、私も通訳の仕事をしていて、聞き取れない英語に出会うことは今でもあります。
通訳だからって、必ず一語一句全て聞き取れているわけではありません。知らない単語が出てくることもあれば、マイクの音声トラブルなどで音が途切れることもあります。
それでも通訳は、よほどのことがなければ、仕事をやってのけることができます。その秘密を知りたくありませんか?
この記事を読めば、以下のことが分かります。
✅ リスニングが伸びない人がやりがちな「聞き方」の勘違い
✅ 通訳の現場で大切にしている「聞く」力が伸びる理由
✅ 「聞く」力を育てる4つのステップ(今日から使えるコツ)
✅ 忙しい社会人が続ける「聞く」習慣の作り方
私の通訳の経験から、リスニングで「聞く」力の育て方のコツをお伝えします。
リスニングが伸びない人がやりがちな「聞き方」の勘違い

リスニングが伸びない原因の多くは、聞き方の思い込みにあります。まずは、どんな勘違いが「聞く」力の上達を邪魔しているかを押さえましょう。
勘違い1:とにかくたくさん聞けば伸びると思っている
「たくさん聞けばそのうち聞き取れるようになる」と思って、ひたすら英語の音を流し続けていませんか?
過去に、TOEIC900点という高得点の学習者さんから、

worthという単語が聞き取れないんです。何回聞いても、耳をダンボにして待ち構えていても、入ってきません。
というご相談をいただいたことがあります。ですが、 “worth” は、前後の音とくっつくため、「ワース」とはっきり発音されることはほぼありません。
こうした「聞こえない音」にしがみついて、何度も同じ箇所を繰り返して聞くより、聞き取れた部分と文脈から意味を推測するほうが、リスニング力は伸びます。
10回聞いて聞こえない英語は、100回聞いても聞こえません。 量だけ増やしても、聞き方を変えなければ、「聞く」力は伸びません。
勘違い2:意味が分からなくても聞き流している
「聞き流し」で、意味を追わずにぼんやり聞いているだけでは、「聞く」力は育ちにくいです。
耳には音が入っていても、「何を言っているか」を追う練習をしていないと、聞き取れた部分から意味を推測する力は育ちません。
BGMのように流しているだけでは、リスニング力はあまり伸びないのです。スクリプトを見ながら意味を確認する」「聞き取れなかったところは原因を分析するといった、意味を追いながら聞く時間を増やすことがコツです。
意味のわからない聞き流しが効果がないことについては、以下の記事に詳しく書いています。よかったら、あわせて読んでみてください!
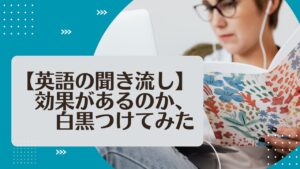
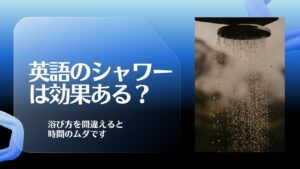
勘違い3:難しいものを聞けばリスニング力が上がると思っている
自分のレベルより難しい教材で、「ほとんど聞き取れない」状態のまま聞き続けていませんか?
後で詳しく述べますが、リスニングには「推測力」が重要です。それなのに、難しいせいで聞き取れる割合が低すぎると、推測の手がかりも少なく、意味をつかむ練習になりません。
難しい英語を聞く練習は、負荷が高くて続きにくいうえに、「何を手がかりに聞けばいいか」も分からず、リスニングは上達しません。
7〜8割ほど聞き取れる、またはスクリプトを見れば意味がすっと分かるレベルの素材を選び、聞き取れる部分を増やしながら「だいたいの意味を取る」練習をすることが、リスニング力を伸ばすコツです。
「聞く」力が伸びる理由|通訳の現場で大切にしていること

リスニングでは、音を一語一句全て拾うことではなく、意味を取ることがゴールです。通訳の現場で私が大切にしていることを、体験を交えてお伝えします。
リスニングのゴールは、「音を全て拾うこと」ではなく「意味が取れること」
通訳の現場では、一語一句すべてを聞き取れなくても、「言いたいこと」が分かれば通訳できます。
実は、通訳でも聞き取れないこともあるんです!力不足で聞き取れない事態は避けなければなりませんが、音声トラブルなど、どうしようもないこともあります。
たとえば、通訳としてある会議に出席していたときのこと。日本人が日本語で発言したのですが、テレビ会議で電波状況が悪く、発言者の男性部長は年配で滑舌も悪く、何を言っているか聞き取れない部分がかなりありました。
これが外国人の発言だったら、「聞き取れない!聞き逃したところに大事な情報があったらどうしよう?」と焦っていたかもしれません。
でも、その時の私は至って落ち着いていました。全部は聞き取れないけど、言いたいことは分かったからです。英語への通訳も問題なくできました。
ちょっと、想像してみてください。
会議の話題が、東京へのオリンピック誘致だとしましょう。話者は日本人で、日本語で話しています。
電話会議で、音声が途切れ途切れで

日本は不景気だし財源がなくて・・・なのに、オリンピックなんて・・・ですよ!
と聞こえたとします。
あなたは、

あー!聞き取れなかった!
と、理解を諦めるでしょうか?
そんなことないですよね。

日本は不景気だし財源がなくて(大変な時)なのに、オリンピックなんて(やっている場合じゃない)ですよ!
とかなんとか、そんな感じのことが言いたいのだと想像がつくはず。
「オリンピックなんて・・・」という言葉の後ろに来るのは、「ありえない」「もってのほかだ」「反対だ」など、普通は否定的な言葉ですよね。
「オリンピックなんて、絶対やるべきだ!」とか「オリンピックなんて、日本を元気にするために必要だ!」とかいう日本語は、不自然です。
つまり、100%聞き取れなくても理解は十分成立するのです。一語一句全てが聞き取れなくても、推測と経験で補うことができます。
聞き取れた単語から、文法や構文の知識をもとに不明瞭な部分を補い、また背景知識や状況、文脈から想像し、そこから「ということは、こういうことを言ってるんだな」と文全体を推測できるのです。
だから、英語も同じことができるようになれば、物理的に聞き取れない部分があっても、ちゃんと推測で補って理解することができるというわけです。
「聞こえた音 + 聞こえない部分の推測 = 理解」
多くの人は、英語に対して「聞こえた音 = 理解」というイメージを持っています。でも、実際は「聞こえた音 + 聞こえない部分の推測 = 理解」なんです。
物理的に聞き取れるかどうかよりも、正しく推測できる構文力や理解力があるかどうかが重要なんです。
聞こえた音 = 理解
聞こえた音 + 聞こえない部分の推測 = 理解
「聞こえない部分の推測」は、以下のような要素で可能になります。
・文法の知識
・単語・熟語の知識
・構文の知識
・よく使われるフレーズ・会話パターンの知識
・その話題や状況についての知識(話の流れ、文化的背景など)
・話者についての知識(思想、ポジション、口癖など)
つまり、これらを身に付ければ、おのずとリスニング力は上がります。全部は聞き取れない文章であっても、推測で補って正しく理解できるようになるのです。
なので、聞き取れない音に対して過剰に執着しないようにしてください。
これからたくさんの英語に触れることで
・正しい英語(文法、構文などの知識)
・自然な英語(よく使われるフレーズ、熟語など)
の引き出しを増やしていくことによって「推測」できる領域を広げていくことです。なので、あなたが英会話のリスニングが正しくできるようになるためにやるべきことは
・単語、熟語、よく使われるネイティブ表現の習得
・文法と構文の知識を固めること
・たくさんのインプットによる英語脳内データベースの構築
です。
「イメージリスニング法」のやり方

「聞こえた音 + 推測 = 理解」の「推測」を支えるのが、聞き取れた単語から頭のなかにイメージ(絵)を描く聞き方です。
多くの人は単語を一つずつ日本語に訳してつなげようとし、

単語はいくつか聞こえたけど、何の話かわからない・・・
で止まってしまいます。ここでは例文を使って、そうならない聞き方のコツを説明します。
まず例文でイメージ化の考え方をつかむ
次の英語を、一度心のなかで聞いてみるつもりで読んでみてください。返り読みは禁止です。
The ancient ruins stood silently bearing witness to centuries of history.
この一文を耳で聞いたとき、あなたはどのように理解しますか?
ここからは、多くの人がやっている聞き方と、目指したい聞き方を分けて説明します。
多くの人がやっている、間違ったリスニングのやり方
The ancient ruins stood silently bearing witness to centuries of history.
この例文を聞いた時の、多くの人の頭の中は、こんな感じになっています。
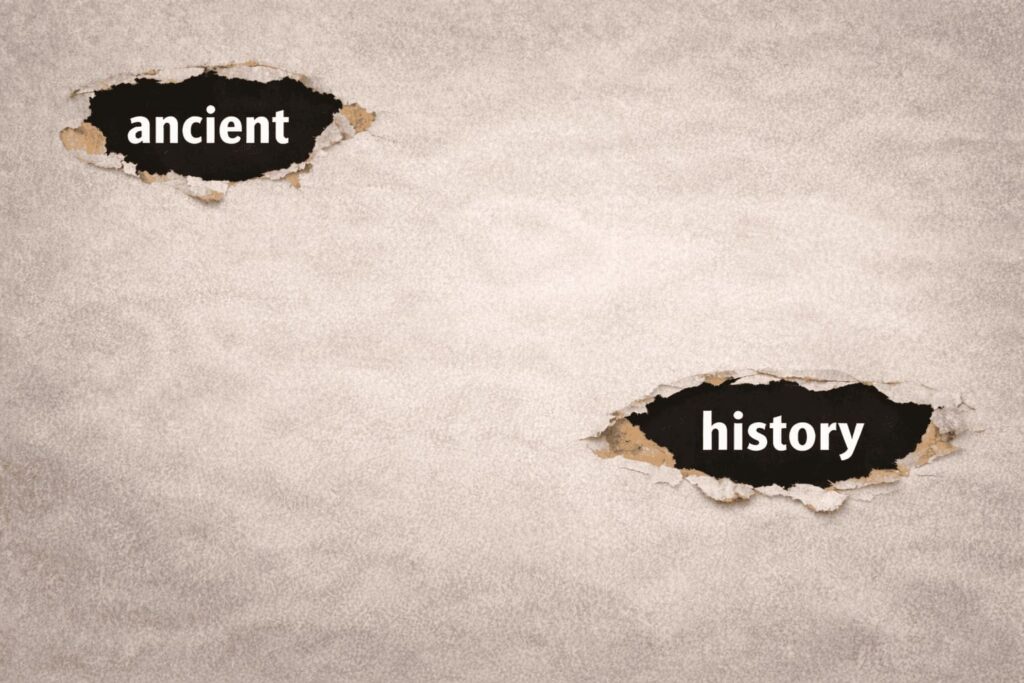

「ancient」と「history」は聞こえた。でも、何の話?

「bearing」や「witness」という、知らない単語の意味が気になって、英語が頭に入らなかった・・・
何度か、同じ英語を聞いてみたら、次はこんな感じになるかもしれません。
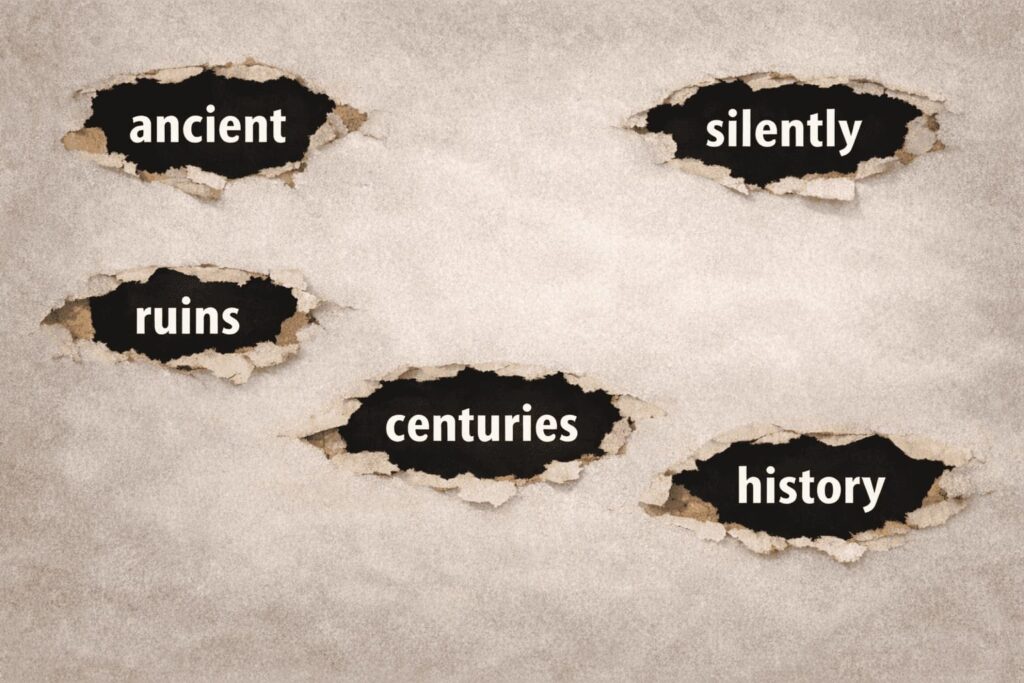

単語は結構聞き取れたのに、話の全体像がつかめない・・・

知らない単語が一つでもあると、「今の単語は何だったんだろう?」と思考が止まり、断片のまま終わる・・・
あなたも、こういう状況に心当たりはありませんか?
「全部の単語を聞き取って、頭のなかで日本語に組み立てないと理解した気にならない」という聞き方をしていると、いつまで経っても「聞ける」感覚が育ちにくいです。
目指したい、正しい英語の「イメージリスニング法」のやり方
The ancient ruins stood silently bearing witness to centuries of history.
この英語で、聞こえた単語から、頭のなかにこのような情景(絵)を描くのが、正しい英語の聞き方(イメージリスニング法)です。

「ancient」「ruins」「history」が聞こえたら、頭の中で日本語に訳すのではなく、
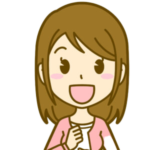
なんか、古い遺跡の話だな〜
と映像で捉える。
古い遺跡が立っている様子を、ぼんやりでいいので思い浮かべるのです。
主語と動詞(The ancient ruins stood = 遺跡が立っていた)さえ聞き取れれば、後半の bearing witness to centuries of history で少々知らない単語が出てきても、遺跡が立っているイメージはできますね。
そして、何度か聞いているうちに、だんだんとその映像がクリアに見えてくる感じです。

bearing や witness がわからなくても、このイメージは作れるのです。
そして、このイメージがあれば、

witnessは確か「目撃する」だったから、「歴史の目撃者として遺跡がそこに立ってる」みたいな感じか!
と、意味が掴めるのです。
聞き取れなかった単語にこだわらず、聞こえた部分からイメージを広げる。これが目指したい「イメージリスニング法」です。
なぜ「単語を並べるだけ」だとリスニングは伸びないのか
聞き取れない単語が出るたびに思考が止まると、いくつか単語は聞こえても断片のままで、話の全体像が見えません。
「全部聞き取れないと分からない」と思い込んでいると、聞き取れない語に引っかかるたびに止まり、いつまで経ってもリスニング力は伸びにくいです。
一方、聞こえた単語からイメージを描く聞き方に変えると、少々聞き取れない語があっても「何の話か」が浮かび、大意がつかめるようになります。
だから、単語を並べて日本語に訳す聞き方から、聞こえた部分から情景を描く聞き方に切り替えることが大事です。
私は、大学時代にフランス語の先生に、「あなたが聞き取れなかった単語は、重要な単語ではない!」と何度も指導されました。今は、先生が言いたかったことがよく分かります。
イメージ化を習慣にするコツ
聞こえた単語から、日本語の意味を思い出すより先に、頭のなかで情景を浮かべる癖をつけましょう。
主語と動詞(誰がどうした)をまず押さえる。そして、聞き取れなかった単語にこだわらず、聞き取れた部分からイメージを広げましょう。
リスニングだけでなく、音読するときや、スクリプトを見ながら聞くときも、字面だけ追わず、内容を映像として思い浮かべながらやると、イメージ化の練習になります。
最初はぼんやりしたイメージで十分です。続けるうちに、聞いただけで「何の話か」が浮かびやすくなっていきます。
「聞く」力を育てる4つのステップ

ここからは、今日から使える「聞く」力の育て方を、4つのステップで説明します。教材の選び方から、スクリプトの使い方、同じ素材を繰り返し聞くまで、順番に押さえていきましょう。
ステップ1:自分に合った教材を選ぶ
まず、自分に合った教材を選びます。知らない単語が多すぎるもの、聞き取れる割合が低すぎる(ほとんど分からない)ものは負荷が高く、続きません。
目安は、8割ほど聞き取れる、またはスクリプトを見れば意味がすっと分かるレベルの素材です。長さは、最初は1〜3分程度の短いものから始めると、繰り返し聞きやすいです。
興味のあるテーマなら、続けやすくなります。
ステップ2:まずはスクリプトなしで1回聞く
最初の1回は、スクリプトを見ずに通して聞きます。ここでいちばん大事なのは、聞こえた部分からイメージ(絵)を描こうとすることです。
・単語を全部拾おうとしない。
・聞き取れた単語から「何の話か」を情景として頭に浮かべる。
・「主語 + 動詞(誰がどうした)」をまず押さえて、大意をつかむ。
上で説明した「ancient ruins」の英語の聞き方(イメージリスニング法)です。
どこまで意味が取れたか、何が聞き取れなかったかも、このときに把握しましょう。聞き取れなかったところは、次のステップでスクリプトと照らし合わせて原因を分析します。
ステップ3:スクリプトで確認し、音と意味を一致させる
聞き取れなかったところは、単語を知らなかったのか、音の変化(つながり・省略)で聞こえなかったのか、構文が複雑で意味が追えなかったのかを、スクリプトで確認します。
たとえば、「シュダ」と聞こえて何なのか分からなかったものが、スクリプトを見ると「should have」のことだった!とわかる、といった感じです。
「シュダ」が何かわからないからと言って、それを何十回も繰り返して聞くより、さっさとスクリプトで確認し、原因を分析して、単語・文法・構文・背景知識のどれを足すかを決めるほうが、聞く力は伸びます。
そのうえで、同じ素材を何度も聞き直します。目的は、耳に入ってくる音と、意味(単語・文の流れ)を一致させることです。
「この音は、この単語・この意味なんだ」と頭と耳で一致させ、正しい英語のリズムや、音がつながって変化している部分を、目で確認しながら聞きます。
あわせて、その英語を音読しながら内容を頭のなかでイメージ(絵)として描く練習をすると、次にスクリプトなしで聞くときにも「何の話か」が浮かびやすくなります。
ステップ4:同じ素材を何度もリスニング・音読をして「聞く」力を定着させる
同じ素材を、何度も聞き直します。一度で完璧に聞き取ろうとしなくて大丈夫です。
回数を重ねるうちに、「この後はこう来る」という予測が働くようになり、聞き取れる範囲が広がります。
そして、その素材を何度もながら聞きしたり、音読やシャドーイングをしてみましょう。
その時は、ただボーっと聞き流すのではなく、意味を考えずに棒読みするのでもなく、必ずイメージ(映像)を思い浮かべながらやってください!
同じ素材でこのサイクルを繰り返すことで、聞く力が定着していきます。
音読やシャドーイングについては、この記事に詳しく書いているので、あわせてどうぞ。

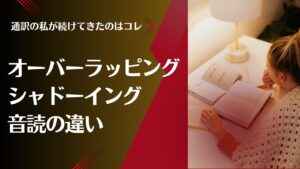
リスニングのコツに関するよくある質問
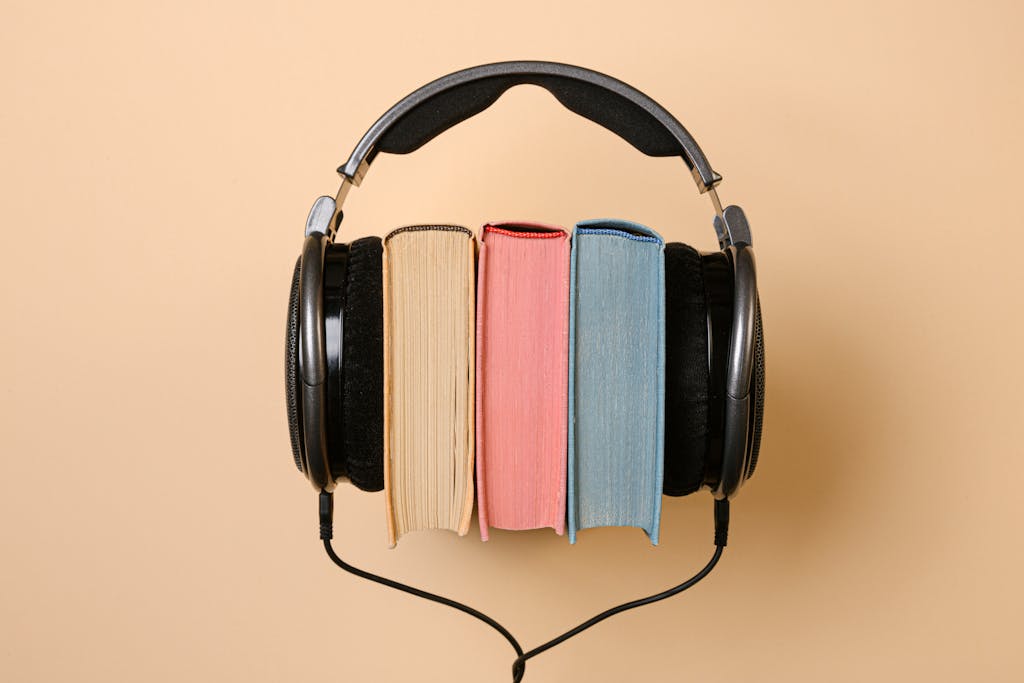
英語リスニングが上達するコツについて、よくいただく質問に答えます。
Q. 聞き流しだけでは伸びませんか?
聞き流しだけでは、「聞く」力はあまり伸びません。耳は慣れますが、意味を追い、推測する練習をしないと、聞き取れる範囲は広がりにくいです。
リスニングの勉強を習慣化するためには、家事や通勤時間などの「ながら聞き」が最も適しています。
その上で、1日の少ない時間でもいいので、「スクリプトを見ながら、聞こえた音とその意味を一致させる」という作業をする時間を取ると、コツが身につきます。
聞き流しについては、この記事をどうぞ。
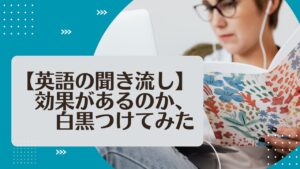
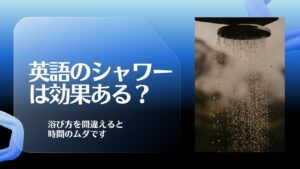
Q. 「聞く」力が伸びるまで、どのくらいかかりますか?
素材の難しさや、もともとの語彙・文法の力にもよりますが、半年ほどで、「前より聞き取れるようになったかも」と感じる方は多いです。
ただ、上達の感覚は本当に得にくいものなので、「いつになったら聞き取れるようになるの?」と心配しすぎないことです。
大切なのは、一語一句聞き取ることを目標にしないこと。聞き取れた部分と推測で、頭の中でイメージが描けるようになることが、伸びているサインです。
上達の実感について、以下の記事に詳しく書いています。あわせてどうぞ!

Q. 発音が苦手でもリスニングは伸びますか?
伸びます。発音とリスニングは関係しますが、すべての音を自分で再現できなくても、聞いて意味が取れるようになることはできます。
よく、「自分が発音できる音は聞き取れる」と言いますが、「発音できない音は聞き取れない」というわけではありません。
発音は苦手でも、高いリスニング力を持っている人はたくさんいます!なので諦めないで大丈夫です。
まとめ|英語リスニングのコツ・聞き方を変えると伸びる
最後に、この記事でお伝えしたことを整理します。
✅ リスニングが伸びない人の多くは「聞き方」を間違っている
とにかく量を聞くだけ、意味を追わない聞き流しや、難しすぎる教材では、リスニング力は育ちにくい。
✅ リスニングのゴールは「全ての音を拾う」ではなく「意味が取れる」こと
通訳の現場でも、100%聞き取れないことはある。聞こえた音と推測で補いながら理解すれば良い。聞き取れなかった単語は、大事ではない。
✅ 聞こえた単語からイメージ(絵)を描く(イメージリスニング法)
単語を並べて訳すのではなく、聞こえた部分から「情景」を頭に思い描き、意味をつかむ。そのために、主語・動詞をまず押さえる。
✅ 聞く力を育てるコツは4ステップ
自分に合った教材を選ぶ → まずスクリプトなしで1回聞く → スクリプトで確認し音と意味をつなげる → 同じ素材を何度も聞いて定着させる。
✅ 続けるには時間・場所を固定し、短い時間から始める
ながら聞きで習慣づけ、集中して聞く時間で力を伸ばす、の使い分けがおすすめ。
これが、英語リスニングのコツです!一語一句聞き取れる必要はありません。
少々知らない単語や聞き取れない部分があっても、聞こえた音と推測で意味が取れるようになれば、怖いものはありません。
今日から、英語を聞いたり読んだりする時に、「頭の中で絵を思い浮かべる」ことに挑戦してみてくださいね。